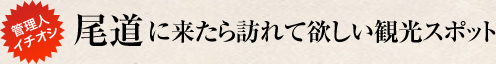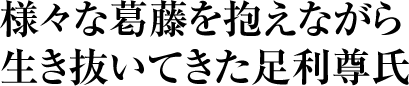
建武の新政は成ったかのように見えたが、天皇・公家を中心とする王政復古の政(まつりごと)を復活させようとする後醍醐天皇と、天皇を君主としながら武家の棟梁として公武合体の政(まつりごと)を行おうとする足利尊氏の思いとは同床異夢の幻想でしかなかった。
討幕が成った後、後醍醐天皇は朝廷の力を強化して中央集権的な国家を目指したが、自らの思いとは裏腹に天皇の委任を受けた太政官が政事を専横して朝令暮改を極めた結果、その都度綸旨(りんじ)(天皇の命令書)が覆り綸旨の価値の低下を招いた。
その上、賄賂や口利きがはびこり近臣達だけが富と権力を集めた。討幕の恩賞も討幕に何ら貢献もなかった京の公家達が厚く遇された。地方の混乱は一層甚だしかった。
一旦土地の所有を白紙に戻し、土地や荘園の給与権は朝廷にあり、またその決裁は綸旨のみによるとした一連の土地制度改革はかえって地方の秩序の崩壊を助長させるものとなった。
後醍醐天皇の建武の新政に不満を持つ東国の武士や旧幕府勢力北条得宗家高時の遺児である時行等の中先代の乱を鎮圧するとの名目で尊氏は建武二年(1335)八月二日、京を出立した。
その際尊氏は後醍醐天皇に旧幕府勢力北条の持つ権力、血統に対抗するため、武士の棟梁たる「征夷大将軍」と全国の守護の監督を司る「総追捕使(そうついぶし)」の二つの官職を要求して出陣を願い出ていたのであるが、後醍醐天皇は尊氏が畿内と西国一円を治める鎮守府将軍であるとの理由で、出陣そのものを認めようとしなかった。
天皇の側近達には尊氏に征夷大将軍などを与えれば鎌倉の二の舞となりかねないとの思惑があった。結局、尊氏は勅許を得ないまま、前年に任じられていた武士に対する軍事指揮権を持つ「征東将軍」として鎌倉に出陣した。鎌倉での反乱は直ちに鎮圧を図らなければ将来に禍根を残しかねない事態であった。尊氏の率いる追討軍の勢いは目覚ましく八月十九日には鎌倉を奪回した。
鎮圧後、後醍醐天皇は再三尊氏に京に戻るよう命じたが、尊氏は旧幕府軍の残党の殲滅やそれまでの武士の慣習を無視した政策に不満を招いていた東国の武士達を鎮撫しておくべきであるとして、そのまま鎌倉に止まって所有地の安堵等の論功行賞を行って帰還に応じる事はなかった。尊氏は東国の土地は既に朝廷から認められているものであるという考えであった。
しかし天皇やその側近達にしてみれば無論尊氏にはそんな権限は与えて無いとして、尊氏の勝手な行動を「許し難し」として官位を剥奪し、建武二年一一月二十二日、尊氏を朝敵と見なし源氏の一門の御家人である新田義貞に追討の宣旨を下した。源氏嫡流と言う点では新田氏の方が足利氏より濃いのに、それまで足利氏の風下に立たされていた新田義貞にしてみればたかが足利如きとの思いもあって、天皇の命を受けた新田義貞の勢いは目覚ましく、元々足利の荘の三河岡崎の矢作の陣も簡単に突破して進軍してきた。
これに対して尊氏はこれを迎え撃っていた弟の直義の身が危ういという報告が届いても、更に新田義貞が箱根まで攻め込んで来ても、建長寺で出家をしようとしたり、もとどりを切って迄、逡巡して中々動かなかった。尊氏は寿永二年(1183)十月、頼朝が後白河法皇との交渉の末、東国の支配権を獲得したように、公家の力の強い京よりも鎌倉で旗を立て鎌倉を固めてから上洛すべきではないか。
後醍醐天皇の新政に直接異議を申し上げるべきではないか。勿論後醍醐天皇に対する畏れ多さと、鎌倉幕府を共に倒したという志を同じくしていた連帯感も尊氏を迷わせていた。尊氏は愈々(いよいよ)追いつめられた結果、天皇の盾となって天皇を惑わしている君側(くんそく)の奸(かん)である新田義貞の討伐を名分として、建武二年十二月八日、やっと重い腰を上げて出陣を決意した。
鎌倉での討幕という活躍により京で武者所頭人(とうにん)に任命されていた義貞を打つことで武力でも実力の違いを天皇側に知らしめようとの思惑もあった。元々京の都とは違って武家政権の樹立の気運の高まっていた関東では尊氏立つとの知らせを受けて不満を持って時機を待っていた地方の武士達が時は今とばかり続々と武家の棟梁である尊氏の旗の下へ結集し、三万をも超える軍勢に膨らんだ。
武家政権の実現をという時代の風潮に清和源氏の嫡流としていつの間にか尊氏は本人の意思とは別の神輿に担ぎ上げられていた。
建武三年(1336)一月、新田義貞を箱根竹之下の戦いで打ち破り、その勢いに乗って尊氏軍は京に入った。
圧倒的な強さで快進撃を続け上洛したものの、尊氏は自分達が天皇に弓を引いてまで武家政権の再興を図ろうなどとはとても畏れ多い事で許されるものではない。自分達が逆賊呼ばわりされることだけは絶対に避けなければならないと考えていた。
尊氏を追って奥州から攻め上ってきた北畠(きたばたけ)親房(ちかふさ)や楠(くすの)木(き)正成(まさしげ)、名和(なわ)長年(ながとし)等の軍勢に攻め込まれて亀岡市の篠村八幡宮に退いた。ここは尊氏にとって三年前の元弘三年(1333)山陰に進軍する途中、柳の木に足利の家紋二つ引両の旗を掲げて鎌倉幕府に反旗を翻し、兵を集めて六波羅探題に攻めこもうと覚悟を決めた場所であった。
再びこの地に立って尊氏はしみじみ自分が望んでいる公武合体の政治体制が何故天皇に理解されないのかが無念であった。どうしても戦う大義を持てない尊氏は苦しんでいた。鎌倉幕府の崩壊後の世の中の混乱を尊氏なりに収拾をしようとすればするほど逆に後醍醐天皇に対立し反旗を掲(かか)げる事態になってしまう事で積極的に戦う意欲が持てなかった。
尊氏は、二月丹波路からさらに後退して明石の海岸に出た。その途中で「うち向う方はあかしの浦ながら尚(まだ)晴れやらぬ わが思いかな」と詠んでいる。それでもまだ尊氏は拘泥し、後醍醐天皇が自分を武士の棟梁である征夷大将軍と認め、協力して公武合体の政(まつりごと)を行っていく事を願っていた。
この様な曖昧な尊氏の態度は足利軍全軍の士気に影響した。戦う組織として態を成す事は難しかった。割り切れぬ思いの中でついに室津の港から西に退かざるを得なかった。西に逃れ始めた足利軍を見て、この時とばかり新田義貞軍等の反撃軍が攻めてきたが、これを赤松則(のり)村(むら)(円(えん)心(しん))が播磨の白旗城でくい止めた。播磨の赤松則村(円心)は京に建武の新政に大功があったにもかかわらず播磨国の国司(長官・守護職)には天皇がお気に入りの園基(そのもと)隆(たか)が任じられ、尚且つ次官格の播磨介には新田義貞が任じられた。
赤松則村はその下の守護職であった。播磨国の本来の守護職を取り上げられただけでなく元の佐用荘の地頭職のままとされ、則村は余りにも理不尽な処遇に後醍醐天皇を見限って尊氏側に寝返っていた。
後醍醐天皇及びその側近達は則村が護良(もりよし)親王の令旨の下で働いていただけではないかとの判断からの処遇であったが、後醍醐天皇及びその側近達には戦いの全体の姿が捉(とら)え切れていなかった。
尊氏は西下しながら最早後醍醐天皇とは求める政体が違う事を認めるしかなかった。よって立つ所の違いは戦いもやむなしと考えざるを得なかった。自らの軍事行動の大義を得るよう赤松則村等の具申もあって持明院統の光厳上皇から院宣(いんぜん)が奉じられるよう差配していた。
光厳上皇にも文保元年(1317)の大覚寺統と持明院統の天皇が交互に在位十年として即位するという両統てい立の和解案を反故にして後醍醐天皇は自らの系統である大覚寺統のみが皇位を継ぐべきだと考え、皇室の内部分裂のきっかけを作った元々の張本人ではないかとの思いがあった。
西下にあたって尊氏は備前の松田氏、讃岐の細川氏、周防の大内氏(長弘)、長門の厚東氏(武実)に協力を取り付けていた。港湾として戦略上重要な鞆の浦及び尾道浦には足利一族の重臣である今川三郎・四郎の兄弟を送り込んだ。
兄弟は尾道浦では光明寺(尾道市土堂町)に陣取って内海の海賊衆を抱き込む為の工作と地元の有力者との折衝等をさせた。
安芸の小早川祐景には自領を安堵することで協力させるよう手を打った。この頃には尊氏は自らの立ち位置を明確に描き始めていた。最早この世の流れは武家政権でなければこの乱れた世の中は収まりが付かない、民衆の為に世を正す御政道を成すのは自分達しかいないと確信を持つようになっていた。
尊氏は後醍醐新政権のもとで取り上げられた土地所有権を元の持主に返付するとの「元弘没収地返付令」を発布して反建武の中興の態度を鮮明に示した。この事は更に旧北条方の御家人等含めて全国の多くの武士に尊氏への支持を表明させ、尊氏の旗の下へ帰属させることとなった。西に退きながらも尊氏の信望は益々確かなものになっていった。
1331年、後醍醐天皇が企てた鎌倉幕府討伐の元弘の変が起こった時、伊予の豪族河野氏の支族であった土居通増・得能通綱や後白河法皇の長講堂領であった忽那島の忽那重義・重清親子、大三島の祝(ほうり)安親は鎌倉幕府に反旗を翻していたが、尊氏が間もなく反後醍醐の意志を鮮明にすると尊氏の軍勢に加わった。
伊予の河野通盛は元弘の変では北条側に付いたが、尊氏が中興政権に反旗を翻すと尊氏の下に駆けつけた。それでも西下の途中で備前の児島に引っ込んでいた後醍醐天皇の忠臣である児島高徳(備後三郎)の動きも尊氏には気になるところであった。
更に備後の吉備津神社南側の丘陵を居城(桜山城)として、元弘の変に応じて楠木正成等の挙兵に呼応(こおう)して反幕府軍としてこの地で立ち上がった宮方の櫻山慈(これ)俊(とし)一族は近隣の豪族たちを味方につけて急速に勢力を拡大し一時は備後半国を抑え安芸や備中にも進出を伺う勢いを示していた。
櫻山の残党等の動きによってはこれを無視出来ず、戦の場合に備えなければならなかった。(現在、吉備津神社の随身門北側に桜山神社が建立されていて櫻山慈(これ)俊(とし)が御祭神として祀られている)又、笠岡沖の塩飽諸島には塩飽海賊がたむろしていた。
彼等は世情の風を読むのも長けていた。芸予諸島を中心に活動をしていた始祖が南朝側であった村上海賊は事から既に反足利の旗色を鮮明にしていた。因島村上家は元弘三年(1333)に大塔宮(護良親王)から令旨が届けられていた。
伊予大島の村上義弘も反幕府親南朝であった。後醍醐天皇は浄土寺に綸旨を下して朝権回復を祈祷せしめ、その為の費用として因島の地頭職を寄進していた。瀬戸内海の制海権を制する事は双方にとって戦いの成否をも決めかねないものであった。その瀬戸内海の海流を熟知している海賊達の動向は読みにくく流動的でどうにでも転んでもおかしくはなかった。
嘉永元年(1169)、備後の尾道浦は後白河法皇の大田庄(現在の世羅町付近)の倉敷地となって、大田庄の荘園米は京に運ばれていた。文治三年(1186)後白河法皇は源平の戦いで敗れた平氏の怨霊を慰める為に、大田庄を高野山根本大塔の用途料として(不断経の財源として)高野山金剛峰寺に寄進した。
大田庄が高野山領になると、それまで尾道浦から京に運ばれていた大田庄の荘園米は高野山に向けて運ばれることとなった。(現実には堺に運ばれて現金化され高野山の収入となった)更に尾道浦の浄土寺は後白河法皇の勅願寺となり高野山より僧等が派遣された。
大田庄荘園米輸送にあたっては在地管人や地頭等とのトラブルが絶えなかった。そこで高野山では寛元三年(1245)高野山領大田庄預所兼雑掌として和泉方眼淵信を派遣した。淵信は弘安四年(1281)尾道浦の曼荼羅寺を政所として荘園米の収納運搬に当たり、商船団を手なずけて次第に豪族化していった、そして遂には一国の守護でさえ及ばない権勢ぶりを誇るようになった。
永享年間(1429~1440)頃になると、尾道浦には高野山領大田庄の荘園米運送船舶だけでも、尾道浦船籍の船が四十五艘にもなっていた。
尾道浦では海上輸送や交易を行う商船団が形成され、守護や領家から年貢米搬送を請負って問丸(廻船問屋)となる者や、新たな商圏を開発して尾道浦を母港にして各地の請所を預かる梶取達が現れ、卓越した操船技術で荘園米等の輸送をこなす瀬戸内海随一の強力な海上輸送能力と経済力を持つ物流交易拠点として成長していた。問丸(廻船問屋)はその海の豪族商船集団達の取り纏め役であった。
和泉方眼淵信と親戚関係かとも言われている航海業者道(どう)蓮(れん)は問丸として尾道浦を舞台にして紀州、奈良、京都、堺などと交易を行い、その勢力は日本各地に及んでいた。
それだけに世の中の流れにも極めて敏感で豊富な情報量と広い視野を持っていた。反撃軍が櫻山等の残党と示し合わせて反足利として西に退いてきている足利軍に攻撃を仕掛けてもおかしくはない状況であったが、淵信や道蓮等は尊氏を支持した。むしろ積極的に尊氏一行を尾道浦に招聘した。今川兄弟の交渉力が功を奏したとも言える。
馬には精通していても海には縁の遠かった関東武者である足利軍にとって西下するにあたって将兵の輸送や食糧の確保、海賊問題、瀬戸内海の激しく複雑な潮流や岩礁などの障害物の多い海域での航行、春から夏にかけて発生する濃霧の中での航行、島嶼(とうしょ)部での海戦等々様々な課題を解決する必要があった。
こうした問題も一挙に解決させる海の豪族商船集団達の支持は尊氏にとって力強い後ろ盾となった。

建武三年(1336)二月十四日、鞆津(広島県福山市)で宿舎としていた小松寺の尊氏の所にやっと待ち望んでいた吉報が届いた。
持明院統の光厳上皇から「諸国の朝敵を退治すべし」との院宣(いんぜん)を醍醐寺の三宝院賢(けん)俊(しゅん)僧正より賜った。尊氏はこれで錦の御旗を掴み、晴れて朝敵という汚名を雪ぎ足利軍の軍事行動が正統化されたことを天下に知らしめる官軍としてのお墨付きを得たことになった。
一気に足利軍の気勢は上がり、今すぐにでも京に引き返して北畠(きたばたけ)親房(ちかふさ)や楠(くすの)木(き)正成(まさしげ)の賊軍と戦うということも選択肢として考えられた。
尾道浦の浄土寺は当時高野山と縁を結んだ後(のち)、奈良西大寺の叡尊(興正菩薩)・忍性・定証と続く律宗寺院の列に連なっていた。淵信は嘉元四年(1306)定証を助けて浄土寺を再興させ、西大寺に高野山領大田庄請所と開発領地等を寄進した。これに拠り事実上浄土寺が高野山領大田庄の荘園米の請所を預かる別当(べっとう)職(しき)をも兼ねた寺院となった。
忍性は清和源氏の本流となる清和天皇の曾孫にあたる源満仲(多田満仲)が創立した摂津(兵庫県)多田院(今日兵庫県川西市にある多田神社)の別当職を任じられて以来入滅に至るまで多田院の修造やその後の維持の為に力を尽くしていた。
浄土寺の阿弥陀堂の御本尊は満仲の嫡子で多田庄を継承した摂津守源頼光が安置したものであり、清和源氏の嫡流たる尊氏にとって自らの祖である摂津守が奉祀した浄土寺の阿弥陀仏に戦勝祈願、足利政権の樹立を願わずにはいられなかった。
二月十七日、御座船に錦の御旗を押し立て尾道浦に入港した。その時源氏の守り神である一羽の白い鳩がどこからともなく飛んで来て一行を浄土寺まで道案内をしたという話が現在も浄土寺では語り伝えられている。
この事は尊氏にとって西下が吉兆となったというだけでなく、尾道浦の浄土寺にとっても浄土寺信仰の霊験(れいげん)のあらたかさを広く世に知らしめる前触れともなったと考えられたのであろう。尾道浦では浄土寺の空教和尚や淵信や道蓮等の出迎えの挨拶もそこそこに、正中二年(1325)大火により焼失後、嘉暦二年(1327)道連・道性夫妻の援助によって再建された真新しい浄土寺観音堂で幹部を集め軍議を開いた。内海の海賊や南朝側の残党対策等軍議は多岐にわたった。
今すぐ京都に攻め上(のぼ)るべきか、九州の肥後国菊池郡(熊本県菊池市)を本拠として勢力を拡大していた南朝方の菊池武重を叩いておく事を優先するべきかで議論は伯仲した。九州の菊池家十三代菊池武重は後醍醐天皇に肥後守に任ぜられていた。
その弟の菊池武(たけ)敏(とし)も尊皇思想の考えは楠木正成にも劣らなかった。

浄土寺本堂
足利軍が官軍として清和源氏の嫡流・武士の棟梁として天下に覇をとなえるためには、ここで京都に攻め入る事よりもまず菊池氏を破って尊氏支持勢力をまとめ、足腰のしっかりした基盤の強化を図っておくべきであるということに決した。
この軍議で方針が明らかになり足利軍の士気は一層高まった。軍議の後、浄土寺本堂で空教和尚が導師となって足利軍の戦勝祈願が行われた。
尊氏は浄土寺に備後国の得良郷(加茂郡大和町)の地頭職を寄進すると共に因島(尾道市因島)の地頭職も安堵して謝意を示した。
因島は塩の荘園としての価値だけでなく、尊氏も後醍醐天皇と同様瀬戸内海を航行するのに流れが速く危険が伴う来島海峡を避け、因島と向島に挟まれた布刈(めかり)瀬戸(せと)が重要な軍事航路である事を承知しており、ここは押さえておきたかった。
二月十九日一行が尾道浦を出港するにあたって募っていた船手を吉和浦(尾道市吉和)の漁師船団が尊氏軍の水先案内を受け持った。
万里小路(藤原)藤房は後醍醐天皇の側近として討幕運動に参画し、建武政権が成った後(のち)は恩賞方筆頭となり、雑訴決断所寄人などの要職を担っており、論功行賞の決め方が不平等である事を後醍醐天皇に諫言していた。
しかし後醍醐天皇には受け入れて貰えなかったことから見切りをつけ突然出家して行方をくらましてしまった。
又、建武の新政の立役者の一人である楠木正成も後醍醐天皇に尊氏の出自の良さやその政策手腕や武士の中での人望等から「新田義貞は見限って足利尊氏と和議を結び、公武合体の政(まつりごと)をすべし」との献策をした。ところが勝ち戦に酔いしれていた天皇及びその側近たちには一笑に付されて相手にされなかった。政の根幹において尊氏と正成とは志(こころざし)は同じであった。
延喜天暦の治世の政治を理想としていた後醍醐天皇にとって武家の警護役、民の搾取の上に成り立っているクーデターの鎮圧程度ぐらいにしか考えていなかった。論功行賞でも圧倒的に公家側に有利な判定がなされ、前線で生きるか死ぬかの戦いをした武家方にとっては使い捨てにされたとの不満が残った。
そういった状況を冷静に見ていた藤房や正成の提言を、自尊心の高かった後醍醐天皇及びその側近達は理解しようとはしなかった。
保元の乱も平治の乱もこの中興も武士の力を正しく読み解けていなかった。天皇に訳もなく所領を取上げられた武士の心は完全に天皇から離れていた。頼山陽の言う庇(かば)ふ所を遺(わす)るである。
建武三年(1336)二月二十二日、尊氏は長門の国赤間の関に着船した。鎌倉に本格的な武家政権を開いた源頼朝に憧れていた尊氏は源平最終決戦のこの地で、源頼朝が再起を期して戦いに臨んだものの、大庭景親ら平氏方と戦った緒戦の石橋山(現小田原市)の戦いで大敗を喫して、ほうほうの態で海を渡り安房(あわ)の国に逃(のが)れていった時の惨めな姿を思い起こしていた。
それを今の自分に重ね合わせていた。尊氏は目の前の壇ノ浦の潮の流れを見つめて源頼朝は負けてなお反乱の炎は一気に関東に広がり草木が靡(なび)くように味方が結集し、遂に本願を遂げた事を思ってしみじみと感慨に耽っていた。
世を正し、民を救うには最早我々の手で政権を奪取する他はないと尊氏は改めて凛凛(りんりん)とした確信を感じて身震いしたのは関門の海風の冷たさだけのせいだけでなかった。
九州に入った尊氏軍は三月二日、筑前(福岡県)の多々良(たたらが)浜(はま)の戦いでは苦戦を強いられていたが、戦中に北風を背に受けるとの幸運もあって南朝方の菊池武敏軍を打ち破り、四月三日にはもう東上を開始した。
多々良浜の勝利の結果、大塔宮からの令旨があって旗色を決め兼ねていた豪族達も続々と尊氏の傘下に結集してきた。五月一日には厳島神社に入り、三日まで参籠し戦勝祈願を挙行した。
その時厳島には多くの軍勢が尊氏を迎えた。その船の数は七千余艘にも及んでいた。その後、東上する主力部隊は向島と因島との間を流れる布刈瀬戸を抜け備後の鞆津へ船を進めさせた。尊氏の御座船と参謀を乗せた小部隊は尾道水道から再び浄土寺に入った。
九州での勝ち戦の御礼と来るべき大戦の戦勝祈願のためであった。尊氏は早速浄土寺の観音堂に幹部を集め、戦勝祈願の法楽和歌の会を催した。各々が観音経の一句一句の偈(げ)文(ぶん)をさぐって詠題として和歌に祈りを託するというものであった。
尊氏の「偈」は「弘誓深如海」で「わだつみの ふかきちかいの あまねさに たのみをかくる のりのふねかな」 (この御座船には多くの願い事を積み込んでいるが、この海の深さと同じぐらい観音様を深く深く信仰しているのだから、きっとこの御座船はその願い事を成就してくれる観音様の船に違いない) と余裕綽々(よゆうしゃくしゃく)であった。
現在、浄土寺観音堂には尊氏が着座していた本堂(国宝)右側の脇陣を足利尊氏参籠(さんろう)の間と呼んでいる。又、浄土寺には尊氏が奉納した自身の花押が押された和歌を含む観音経偈三十三首の法楽和歌(国指定重要文化財)が残されている。

吉和太鼓踊り
尾道浦を出発するのにあたって、尊氏は浄土寺の観音堂に取付けてあった扉の戸板を外させ御座船に積み込ませた。
この事は単に矢玉除けと言うだけでなく尊氏の観音信仰の深さと、我が軍は観音菩薩の御加護の下、必ず事は成るとの想いを皆に示させた。
更に尊氏は九州へ西下する際、水先案内をしてくれた吉和浦の人々には内海で漁労が出来る特権即ち漁業権を付与することも忘れなかった。
吉和浦の人々はこの事に感激して戦勝祈願にと鉦や陣太鼓を打ち鳴らすだけでなく、手の空いた者は船端を叩き大声を張り上げて声援を送り、鞆の沖まで足利軍を見送った。その様子を再現して、現在吉和浦の漁民達に引き継がれている踊りは、尊氏の御霊を載せた御座船が浄土寺の長い石段を上がる時には踊り手は全員御座船の後ろの守りながら石段を後ろ向きに上がっていく。
その際の掛け声は正に戦いに臨む思いを基本にしているだけに甲冑や戦闘等に関する台詞が多く採用され、歌の途中でエーイ・エーイと声を掛け合う大変勇ましい踊りである。この踊りが「吉和太鼓踊り」として広島県の無形民族文化財となっており「吉和太鼓踊り保存会」によって隔年の八月十八日に浄土寺に奉納されている。
足利軍に加勢して西下し、多々良浜の戦いで大功を果たした備後国椙原保の豪族・杉(すぎ)原信(はらのぶ)平(ひら)、為(ため)平(ひら)兄弟に対して尊氏は信平の甲冑の背につけた母衣(ほろ)に「西国一番の働き比類なきものなり」と自ら書き記(しる)して賞賛した。
兄弟の父親杉原胤(たね)平(ひら)は元弘元年(1331)南朝側に味方して旗上げをしていたが、兄弟は尊氏の下に馳せ参じた。兄弟はその後も足利軍と共に行動して湊川の戦いだけでなく、京にも出陣して数々の武勲を立てた。
尊氏はその恩賞として兄弟に備後国木梨庄十三箇村(小原、梶山田、木梨、市原、白江、三成、猪子迫、栗原、吉和、木原、久山田、後地、尾道)を与えている。その後、兄弟は建武四年(1337)木梨(尾道市木之庄町)に鷲尾山城を築いた。
子孫も杉原元(もと)恒(つね)など有能な人物が出て尾道浦に権現山城(千光寺山城)を築き、尾道浦の守護代も務め、高野山領の年貢米の請所を預かる浄土寺の外護にもあたっている。
尊氏は鞆の浦より軍を陸海二手に分けて京を目指した。其頃には九州、四国、中国の武士が足利軍に結集していた。
「太平記」によると「鞆の浦より直義を大将に二十万騎を差し分ちて陸上を、尊氏は一族四十余人、高家一党五十余人、上杉の一類三十余人、外様の大名百六十頭、兵船七千五百余艘を漕双べて、海上をぞ上せられける」とあるが、実際には九万の兵に直義を大将に付けて陸路を東上させ、残り三万は水軍として総大将の尊氏が率いてお互いが連動しながら湊川を目指した。
(諸説あり)「梅松論」では「尊氏の本隊の船団幾千艘、皆帆を揚げ、淡路の瀬戸五十余町、湮波湮渺(えんばようびょう)たる海上を唵(おお)ひ到り、鼓噪喊呼(こそうこんこ)して東進しぬ」と記している。
建武三年(1336)五月二十五日、摂津(兵庫県)の湊川で楠木正成軍を討ち果たし、正成を自害に追い込んだ。
正成は後醍醐天皇に一旦比叡山に退いて頂き、京の中で足利軍を新田義貞と挟み撃ちにするとの対尊氏の戦いの作戦を言上するも側近がそれを許さなかった。
正成は勝ち目のない戦いに臨まなければならなかった。尊氏は宿敵新田義貞を敗走させ、五月末には上洛して京を制圧した。十一月には持明院統の光明天皇が即位した。十二月、後醍醐天皇は吉野に移り、吉野で新たな朝廷を開き尚自らが天皇であることを主張した。
南北朝の対峙が始まることとなったが、尊氏は後醍醐天皇が吉野を南朝の本拠地としたことについて「天下は落ち着くべきところに落ち着くものだ」とどこか世を覚めた目で俯瞰(ふかん)している。
尊氏にとって絶頂期というべきこの頃、尊氏は清水寺に(京都市東山区)に「もし自分にこの世で与えられる果報があるとしたなら、その果報は全て弟・直義に譲って欲しい。何(なに)卒(とぞ)直義の身が安穏であるよう御加護を賜りたい。」との願文を納めている。
尊氏の無欲で私心が無いこんなところに多くの武将達の心を惹き付けさせていたのであろう。
建武三年(1336)十一月七日、尊氏は実質室町幕府の施政方針である「建武式目」を示した。暦応元年(1338)八月十一日には光明天皇から征夷大将軍に任ぜられて二条高倉に室町幕府を開いた。
一方、吉野に逃れた後醍醐天皇は「ここにても雲井の桜咲きにけりただかりそめの宿と思うに」と暫(しばら)くここで耐えていれば京を奪回する事も叶うだろうとしたが、遂に果たせず、「玉(み)骨(こつ)は たとえ南山の苔に埋(うずも)るとも 魂魄(こんぱく)は常に北闕(ほっけつ)(宮城)の天を 望まんと思う」(太平記)と無念さを滲ませながら暦応二年(1339)八月十六日吉野で崩御される。
「君子南面す」ではなく御陵(塔(とう)尾(おの)陵(みささぎ))はこの遺言の如く京の方向である北、正に「北闕(ほっけつ)の天」を望んで造営されている

後後醍醐天皇の崩御に対して尊氏は当時仏教界の第一人者であった夢窓国師の進めもあって天皇の菩提を弔うため光厳上皇の院宣を受け嵯峨野に天龍寺を建立した。
天龍寺の正式名称は「霊(れい)亀山(きざん)天龍資聖禅寺」であるが「天龍」という言葉は、弟の直義が大堰(おおい)川(がわ)(渡月橋より上流)に巨大な金の龍が天に昇る夢を見たことによるとされ、「資聖」というのは後醍醐天皇の怨念を鎮め助け奉(たてまつ)るとの意味である。
もともとこの地には南禅寺を開いた大覚寺統(南朝)の初代天皇である亀山天皇の離宮があった場所で条件が整っていた。
幕府はこの造営資金を得る為、交易船「天龍寺船」を元に送り出している。勿論瀬戸内海が幹線航路となり、尾道浦はこの天龍寺船団の交易の拠点として大いに賑うこととなった。
暦応二年(1339)には尊氏は怨(おん)親(しん)平等(びょうどう)(仏法の世界には敵味方の違いはない、怨親ことごとく平等ならんことを願う)との夢窓国師の勧告に従って国家の安寧と護持、敵・味方を問わず北条氏討伐以来の戦乱で亡くなった大勢の人々の霊を弔うべく全国に一寺一塔(安国寺と利生塔(りしょうとう))を建立することを決めた。
備後国では鞆の浦に安国寺(この安国寺は鎌倉時代に法燈国師を開基としてここに創建されていた金宝寺を利用したものである。この安国寺は戦国時代一時衰退するが後に安国寺恵瓊(えけい)が再興している。現存する仏殿は唐様建築で下り棟の止め瓦には見事な龍頭瓦が配され、庭園は重森三玲氏が復元している)を、利生塔は尾道の浄土寺領内に五重塔が新築された。
瑠璃山の中腹に聳え立つ五重塔は尾道にはびこっていた海賊への威圧と順撫とする狙いもあったとも言われている。(浄土寺にはこの五重塔の由緒書きが残されている。この利生塔は現在の尾道市生涯学習センター(元筒湯小学校跡地)のグランドの中央あたりに建てられていた) 尊氏は貞和元年(1345)この建立費として櫃(ひつ)田(た)村(三次市君田、優良な砂鉄の産地であった)の地頭職を浄土寺に寄進している。
この利生塔は江戸時代初期正保元年(1644)塔の鳥の巣を除去しに行った時使用した松明(たいまつ)の火が移り延焼、焼失するが、浄土寺にはこの塔に取り付けられていたという鉄製の燈(とう)籠(ろう)が二基残っている。
又、弟の直義が国家と民衆の安寧を願ってこの利生塔に寄進したという京都の東寺(京都市南区)にあった仏舎利(釈迦の骨)が一粒納められた金銅製の宝珠形舎利容器も残っている。直義は又、浄土寺領内及び寺辺での殺生禁断を命じる書状を出すなど浄土寺に特別な恩賞を与えている。
浄土寺にはこの他、尊氏により母の菩提を弔う為に書かせたという「如意輪観音画像」や陣中肌身に付けていた「陣中念持仏」なども奉納されている。又、尊氏は五重塔の塔婆料所として金丸名(かねまるみょう)(福山市新市町)・上山村(府中市)の地頭職と草村(府中市新市村)の公(く)文(もん)職(荘園の事務を司り、年貢の徴収などを行う部署)を浄土寺に寄進して手厚く保護している。
浄土寺では尊氏の恩顧に報いるため、「尊氏将軍画像」を描かせた。現在浄土寺に残されている尊氏の「肖像画」は束帯(そくたい)姿で笏(しゃく)を持ち、向かって左を向いている。
袍(ほう)には足利家の家紋である桐文が施され、面(おもて)部の垂れ目、大ぶりの鼻や下膨れの頬等、これまで教科書に載っていた「残ばら髪の騎馬像の肖像画」ではなく、今日ではこちらが尊氏の本物の肖像であろうということになっていて、NHKでも採用され放映されている。
寺ではまた尊氏が没して後に供養のための宝篋印塔(ほうきょういんとう)を建立している。
これら浄土寺に対する外護の他に尊氏は尾道浦で時宗の常称寺(尾道市西久保町)には暦応三年(1340)七堂伽藍という広大な寺を建立し、西江寺(尾道市東久保町、現西郷寺)には文和二年(1353)仏餉料(ぶつしょうりょう)二万貫という大枚と尊氏が所持していた陣中念持仏である阿弥陀如来座像を寄進している。同年常称寺の大門を再興している。
同じ尾道の中で、足利家の拠り所である臨済宗天龍寺派の総本山天龍寺の末寺である天寧寺(尾道市東土堂町)は、やっと貞治六年(1367)になって夢窓疎石の甥である春屋妙葩が開山となって建立された。
それも尊氏本人ではなく尊氏の遺志(尊氏は明暦四年(1358)に亡くなっている)を継いだ二代将軍足利義詮による創建であった。関東武者達にとって地盤の無い慣れない西国での戦いという中で、遊行上人、もしくは常称寺、西江寺に関係する職能集団又はそのトップ達が軍資金、武器、武具造り、情報収集、医療等々の職能集団の持つ特殊な技能・能力を惜しまず使って足利軍の勝利に向けて力を注いでくれた。
尊氏にとって自らの信仰上の拠り所である天寧寺よりも先ず時宗寺院に対して寄進する事で感謝の念を示したかった。或いは苦戦していた菊池軍との戦いで風上に陣を取れたのも偶然では無かったのかも知れない。
尊氏にとってこうした備後の鞆の浦や尾道への外(げ)護(ご)の目的は足利軍の反転大勝利のきっかけとなった土地への思い入れというだけでなく、寺院新築等によって鞆の浦や尾道の安寧な秩序の維持を図ると共に、瀬戸内海の中央部にあって「潮待ち」「風待ち」の自然任せの航海を強いられていた当時の交易の中にあっても既に大きな発展を遂げていた鞆の浦や尾道を幕府の交易港として物流の拠点として活用することで幕府の経済力の基盤を固めようとする狙いや、有事の際には大田庄の政所・倉敷地である尾道浦を兵糧米貯蔵庫として利用しようとの思惑もあった。
実際に天龍寺船団の拠点だけでなく、足利義満の時代になってからも明との交易が開かれると、鞆の浦や尾道は勘合貿易の「対明貿易船団」の寄港地として大きく飛躍することになった。
特に尾道から赤胴(金と銅との合金)や中国山地から採れる玉鋼を使って明では神刀としてもてはやされた日本刀十数万振り(本)が輸出されている。鞆の浦や尾道浦では港を中心として航海業者や鍛冶工や石工等地元のあらゆる産業の活性化に繫がった。
室町幕府の幕政を推し進めていく中で、将軍方(尊氏・高師直(こうのもろなお))と副将軍方(直義・直冬)と宮方(南朝)が入り乱れ、政局は混迷の度を深くしていった。
状況に順応することの中から政治の流れを汲み取ることにかけて特異な才能を発揮して時代を生き抜いてきた尊氏であったが、延文三年(1358)四月三十日、背中に出来た悪性の腫物が原因で五十四歳の波乱の人生の幕を閉じた。遺骸は京都衣笠山の麓の等持寺(京都市北区等持院北町)に葬られた。
等持院境内に樹齢四百年になる椿の大木があるが、足利政権が倒れて四百年との長い間健気に咲いては散る事を繰返して来たのには、この木が余程何か伝えたい特別な思いがあるのであろう。どうして自分が大猿と揶揄(やゆ)されなければならないのか、何故未だに朝敵の汚名を着せられているのかが納得がいかないのではないか。
それを尊氏に代わって訴えているのではないか。尊氏の真実の心を気付いて貰いたいと託しているのではないか。
そう考えると咲いて緑の苔の上に落ちている赤い椿の花に何故か尊氏がだぶって見えてくる。分かって貰う迄は何としてもこの木を枯らす訳にはいかないということなのだろうか。それとも真実が分かる人にだけ分かってもらえればそれで良いということなのだろうか。椿の花の花言葉は「控えめな美しさ」である。
小松寺(福山市鞆町後地)
この寺の創建は安元元年(1175)、父平清盛と厳島神社へ参詣の途次、長男平重盛が鞆津に立ち寄った際に自作の阿弥陀仏を祀る一宇を建立した事が由緒とされている。「忠ならんと欲すれば孝ならず、孝ならんと欲すれば忠ならず。
進退これにきわまれり」とは頼山陽の日本外史に出て来る重盛の台詞であるが、重盛は小松寺の庭に小松を植え「若しこの松が天に伸びれば平家は栄えるであろう。地に逼(は)えば平家は衰退するであろう」と言って立ち去ったと伝えられている。
後日、一門の武将平貞(さだ)能(よし)によって重盛の遺髪がこの寺に納められた。当寺では昭和三十年代に地に逼っていて枯れ死したこの松の根元の一部を磨いて置物として庫裏の玄関に飾っている。
元亀4年(1573)七月、足利十五代将軍足利義昭は織田信長に京都を追放され、諸国を流浪の果て、天正四年(1576)2月、毛利を頼って流れ着いたのがこの鞆津の小松寺であった。
義昭が毛利輝元等に庇護されていたこの時期の室町幕府を「鞆幕府」と呼んでいる。その後、織田と毛利の和睦により足利家は十五代義昭で亡んだ。
足利尊氏が建武三年(1336)二月、この小松寺で持明院統の光厳上皇からの朝敵討伐の院宣(いんぜん)を賜っているところから「足利氏は鞆で興き、鞆で亡んだ」と言われている。
小松寺の山号は萬年山、御本尊は観世音菩薩。標柱(しめばしら)には妙心寺派、小松禅寺と刻んである。残念乍ら今は往時の盛況は偲べない。
浄土寺(尾道市東久保町)
浄土寺の歴史は古く推古天皇の御代、616年聖徳太子の草創と言われている。正式名称は「転法輪山大乗律院荘厳浄土寺」という。なにやら修験道場のようであるが、現に奥の院に至る山道には修験者が岩場に取り付けた鎖場もある。
文治二年(1186)大田庄の荘園が高野山領になると浄土寺は後白河法皇の勅願所となった。鎌倉時代末期には教線を広めようと律師・叡尊の弟子である定証(じょうしょう)上人が当時荒れ寺となっていた浄土寺の再興を里人から懇願され、和泉方眼淵信等の援助により、奈良西大寺派の真言律宗寺院として嘉元四年(1306)七堂伽藍の落慶法要を行っている。
ところが、正中二年(1325)の大火により、堂宇をことごとく灰燼(かいじん)に帰してしまった。それでも浄土寺との尾道浦の人々の信仰は深く、尾道浦の問丸であり豪商の若い道蓮・道性夫婦等によって明暦二年(1327)、観音堂(現在・本堂、国宝)、元徳元年(1329)には多宝塔(国宝)、暦応二年(1339)には利生塔(五重塔・現在焼失)、貞和元年(1345)には阿弥陀堂(重文)等々の堂塔が建ち並び、備後国随一の寺院として人心を掌握するところとなって今日に至っている。
この間一旦は西下していた足利尊氏は再び息を吹き返えし、湊川の戦いに臨んで建武三年(1336)五月五日浄土寺で戦勝祈願をし、一万巻の観音経を読経して、法楽和歌三十三首の奉納をしている。出陣にあたっては本堂の戸板を外して御座船の矢玉除けとした。尊氏の観音信仰のあらわれである。

足利尊氏墓所(等持院)
浄土寺には尊氏の供養塔と伝えられている宝筐印塔(ほうきょういんとう) (墓碑塔)と弟直義の供養塔と言われる五輪塔が二つ並んで立っている。
浄土寺の由緒書によると「尊氏の供養塔と伝えられている宝筐印塔は高さが百九十センチで、塔身の四方に金剛界の四仏の種字を刻してあり、基礎・基壇の間に反花座(かえりばなざ)を設け、基礎の側面には大きく見事な格(こう)狭間(ざま)が作られている。南北朝時代における中国地方の宝筐印塔の代表作である。」と書かれている。
江戸時代になって「御寺(みでら)」とも呼ばれる京都の泉涌寺(せんにゅうじ)派(京都市東山区泉涌寺山内町)に属し、現在に至っている。
浄土寺の前住職・小林海鴨師は先年京都泉涌寺の長老(管長)もされていた。
因島(尾道市因島)地頭職
古来より瀬戸内海は京・大坂と西日本、そして国外へと続く海の道であった。
現在でもその瀬戸内海の中央にある芸予諸島を通過するには、日本三大急流と言われている来島海峡を通過しなければならない。当時は比較的潮流が穏やかな因島と向島(尾道市向島)の間にある布刈(めかり)瀬戸(せと)を利用した「沖乗り」航路に対して、専ら(もっぱ)「地乗り」航路と呼ばれていた鞆の浦・阿伏兎観音・尾道を通るルートがあった。
元弘三年(1333)十一月、後醍醐天皇は浄土寺に綸旨を下し、朝権回復を祈願せしめ、その用途料として因島の地頭職を寄進している。これを追認するような形で建武三年(1336)二月、足利尊氏も浄土寺に対して因島の地頭職を安堵している。
尾道浦は大田庄の倉敷地として年貢輸送等海を生活の基盤として活動する人々で賑わっていた。浄土寺はそう言った人々の信仰心に支えられていた。後醍醐天皇も尊氏も瀬戸内海航路の中心にあって潮流のやや穏やかな布刈瀬戸の航路、向島と尾道の間を流れる波の静かな尾道水道と風待ち潮待ち港としての尾道を高く評価していた。
又、いざという時には大田庄の倉敷地を兵站として利用価値があると考えていた。ただ建武三年二月の尊氏は戦いの大義が見いだせず京洛の戦いには積極的に抗戦せず敗れて西下していく途中、尊氏は西走するにあたって「東寺」に戦勝祈願した際、もしこの戦いに勝って帰れたら楠木正成の地盤である河内国の新開庄を寄進する事を約束していた。
結果、尊氏は勝ちあがって東上したが、河内国の新開庄の寄進を受けた「東寺」から新開庄は荒地で年貢がさっぱり上がらないとクレームが来た。
「東寺」の御機嫌を損ねては一大事と、建武五年(1338)正月、尊氏は浄土寺から因島の地頭職を取り上げて、「東寺」に替地と言う事で寄進した。浄土寺こそいい迷惑な話であった。
等持院(京都市北区等持院北町)
臨済宗天龍寺派。山号は万年山。本尊は釈迦牟尼仏。暦応四年(1341)足利尊氏が夢窓疎石を開山に請じて衣笠山南麓に創建した。
尊氏は戦乱が治まり天下が自分の手に帰したならば、必ず三つの寺院を建て、国家の安寧を祈るつもりであると語っていたが、不安定な状態が続き、なかなか三つの寺を建てられそうになかった。
そこで尊氏は、禅僧・古先印元(こせんいんげん)を開山として建てたのがこの等持寺で、寺号には三つの「寺」という字が入っていることから、これで願いを叶えることが出来たと尊氏も喜んだと言われている。
延文三年(1358)尊氏の法名「等持院仁山妙義大居士」から寺名も等持寺から等持院と改められた。
歴代の足利将軍の廟所に相応しく十刹の第一位となり隆盛したが、幾度かの災禍にあい現在の伽藍は文政元年(1818)に建立されたものが中心となっている。(等持院由緒書による)
霊光殿には尊氏の念持仏とされた地蔵尊を中心に右に達磨大師と左に夢窓疎石の像が両脇に祀られ、尊氏以下歴代足利将軍の木造(五代と十四代を除く)が安置されている。
等持院殿(尊氏)の木造の正面に、何故か四十二歳の徳川家康公の木造が置かれている。大徳寺総見院の木造織田信長座像のお顔に似た六代将軍義教の神経質そうなお顔も印象的である。
方丈北側の池全体が蓮の形をした芙蓉池と心字池との間に尊氏の墓である宝筐印塔(ほうぎょういんとう)がある。塔の台座は四面に格(こう)狭間(ざま)があり、宝(ほう)瓶(びょう)に蓮(れん)花(げ)を挿した紋様があって室町時代の形を示している。
三方を綺麗に手入れされた植木に囲まれるようにその塔は建っているが、二百年以上の足利幕府を開いた人物の墓としては驚くほどこじんまりとしたものとなっている。
現在アメリカのメトロポリタン美術館には尊氏が篠村八幡宮に奉納したという鎧が収納されている。
その鎧の板の部分には「不動明王」が描かれている。「不動明王」は戦勝祈願の印とされているが、尊氏がこの「不動明王像」を用いたのは、政治判断・状況判断をするのにあたって出自の良さからか「仁愛」を成して「義」に報いることを優先してしまったことで、合理的に且つ大胆に素早く割り切ることが出来なかった裏返しの様な気がする。
尊氏の優しさが邪魔をして様々な葛藤を抱えながら生き抜かなければならなかった尊氏が、煩悩を断つと言う不動明王に縋(すが)ろうとした思いが感じられてならない。足利尊氏の先祖は清和天皇で源氏の棟梁八幡太郎義家であるのみならず先祖の妻は源頼朝の義妹であり、鎌倉幕府の御家人の中でも筆頭格の家柄であった。
北条得宗家からは正室を迎え、足利高氏の「高」は執権北条高時の「高」を与えられており、周りの人々に大事にされて育った。晩年尊氏が詠んだ「いそじまでまよひきにけるはかなさよただかりそめの草のいほりに」と四十にして惑わずどころか五十までも尊氏の悩みは尽きなかったと言うこの歌にも尊氏のいかにも人間的で正直で素直な人柄が伺える。全く「逆賊」「朝敵」というにはそぐわない。
一つ一つ、その都度の場面場面で尊氏の政治判断が全て正しかったとは思わないが、迷い苦しみながらも激動する時代を懸命に生きて確実に時代を鎌倉から室町へという新しい歴史の一ページを開いていった。
それは間違いなく大局を見通す事が出来ず時代の流れに逆らった反動の道ではなく、正に時代の要請であった。
等持院の境内を散策していると北側にある大学の構内から学生達の元気な声が聞こえて来るが、その声に尊氏が「君達もこれからの人生で色々悩み迷う事があるだろうが、誤解を恐れず突き進んで行って欲しい。
次の新しい時代を動かすのは間違いなく君達なのだから」とそんな風に言っているように思えて胸が熱くなって来た。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット