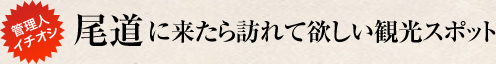![]()
文禄元年(1592)三月二十六日、秀吉は明の征服という自らの壮大な夢の実現のため肥前名護屋に向け、天下人に相応しい艶(あで)やかな行装で足利十五代将軍義昭等を従えて、京(聚(じゅ)楽第(らくだい))を出発した。
秀吉はあえて海路を避け、陸路で山陽道を西に下った。天正十一年(1583)四月二十四日、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を滅ぼしてからほぼ天下を掌握すると、矢継ぎ早に刀狩り、検地、農兵分離、楽市・楽座などの政策を打ち出して自らの政権の安定を図るだけでなく、権勢慾に溺れた秀吉の野望は留まるところを知らず更に朝鮮出兵へと進んで行ったのである。
兵庫、明石、姫路、網干、赤穂、片上、岡山、矢掛と古代山陽道の泊まりを重ね、四月七日、毛利領内の備後の沼隈郡三方村(現、福山市山手の三宝寺)の宿に到着した。
翌日は備後国御調郡市村から仏通寺越えで、三原の本郷(三原市本郷町)の高山城へと進む予定であった。その途中で備後国総鎮守である御調八幡宮に参詣して戦勝祈願に立ち寄ろうと考えていたが、御調八幡宮の八幡町(三原市八幡町)近くの野串の辺りに河野家の残党が待ち伏せをして襲撃(しゅうげき)を企てているとの情報が入り、急遽予定を変更して、沼隈郡今津より西村、西村の森実から擂木を経て大番さんと呼んでいた番所のあった峠を越えて猪子迫を通り、御調郡三成村へと進んだ所で藤井川沿いの三成村三成八幡宮の豊岡宮司宅で休憩をとった。(因みに豊岡家の屋号は「茶屋」である)さらに白江村、本郷村、中野村、三原深村、山中村を通って駒ケ原を南下して中乃町へと抜け、永禄十年(1567)小早川隆景が沼田川の本郷地区にあった新高山城から沼田川の河口に新しく移し替えた三原城に着いた。四月九日の事である。
三原城は三原浦の桜山の南の海中にあった大島・小島を繋いで築造されたもので、海に向って船入を開き、軍港と城郭の機能を兼ね備えた城で、満潮時には海に浮かんでいるように見えるところから別名を浮城とも呼ばれていた。
秀吉はここでしばらく滞留した。三原城には派手好きな秀吉用に誂えた金の間という広間まで設えてあった。備後の御調八幡宮には現在武運長久を祈願した秀吉が自らの手で植樹した桜の木の枯れた根っ子だけが残っている。
野串で待ち伏せをしていた河野家家臣の三百人は伊予の太守湯築城城主河野通直を死に追いやり、五十九代続いた河野家の再興の望みを断った秀吉を恨み、八幡の藪に潜伏して狙撃せんものとしていたが、露見し後日この事件に加担した者は全員捕らえられ処刑された。今でもその時の犠牲者の墓石群が三原市八幡町野串の山中にある。
前年、秀吉は全国の武将に征韓の号令を発しており、西国の雄である毛利輝元にも毛利軍を主力として朝鮮に渡海するよう厳命していた。「太閤記」の記すところによると、その大綱は一、東は常陸から南海を経て、四国、九州沿岸の諸国、並びに九州海岸の国々は、其高十万石毎にたいして大船二艘を用意させ、二、水夫は浦々の家百軒毎に十人宛出させ、三、その扶持は一人毎に二人分並に妻子にも扶持を与えることを命じ、四、これらを二十年春、摂、播、泉州の海岸に集結して命令を待たせる。
それまでの間に秀吉は肥前名護屋に大本営を移すというものである。いよいよ出征が近くなると「高麗罷渡御人数」の事として、各々の部署を明らかにしているが、第七陣に毛利輝元の陣営として三万人、小早川隆景には第六番編成として一万五千七百人など総勢二十八万人もの動員をかけた。
艘の数だけでも輝元の領有石高は百二十万石であるので、大型軍船百四十艘、隆景は一族五十万石なので二十五艘の用意がいる事になったわけである。まさに毛利領の兵力を根こそぎにせんばかりの大動員であった。このため毛利領内の津々浦々から船頭や水夫が集められ、海を渡れそうな船はことごとく借り上げられた。それでも足りず各地で船作りが行われていた。
秀吉の御座船となる日本丸の建造も毛利に下命されていた。この日本丸は、十八畳敷きの座敷が三つもあり、船内で能が上演できる程の大船であった。現在、この日本丸の一部が舟廊下として琵琶湖に浮かぶ竹生島に残っている。又、京都高台寺の開山堂にも御座船の天井であったと言う格天井がはめ込まれている。
これら兵站の段取りは輝元の命を受けた毛利の御用商人渋谷家(大西屋)が普請奉行となって斡旋していた。武器・弾薬等の軍需物品の調達だけでなく朝鮮への輸送には渋谷家が持ち船を出して船団を組んで渡海に応じていた。
毛利側の負担はこれだけでなく、リレー式輸送の次船の設置や諸大名が西下する毛利領内の道路や橋の普請、秀吉の通過する道路の両脇に松の植樹、道すがらの休憩所となる御茶屋の設置等多岐に亘っていた。現在、尾道市の中心部の本通りである商店街(西国街道)もこの時の普請で原形が出来上がったものである。
四月七日、神辺の宿所から秀吉は毛利輝元宛に「毛利領内の宿所は普請、饗応共にあまりに入念で痛み入った。これ程までにされなくてもよいのに云々」と満足の意を伝えている文書が残されている。秀吉の得意のリップサービスとも言えるが、輝元にとっては頭の痛い大仕事であった。
それに秀吉は国々に秀吉の到着の数日前「他国者を国内に滞在させてはならない。但し、確かな証人が居れば、他国者であってもこの辺りに居住している理由と、どのぐらい居住しているかなどを明らかにして、この者は決して怪しい者でない旨を誓紙血判して、その証文を本人に渡しておく事。
但し、昨年七月以降居住の者は滞在を許さぬ。」との不審者の侵入を防ぐ触書を出している。輝元ならずとも骨の折れる大変な仕事であった。あの大気者と言われた男がすっかり神経質になっていて警戒を怠りなかった。
天正十五年(1587)、秀吉によって催(もよお)された北野大茶会での触書は「茶湯執心とあらば、若党、町人、百姓巳下(いげ)(以下)によらず釜一つ、釣瓶(つるべ)一つ、吞物一つでもよい。茶のない者は、焦(こ)がし(はったい粉)にても苦しゅうない。
持参すべし」「日本の事は申すに及ばず、いやしくも数寄の心がけある者、唐国の者までもまかり出よ」「このたびまかり出ない者は、今後、こがしを点てることも無用である。まかり出ない者の所へ参ることも無用と心得よ」と書かれ、北野天満宮の境内に茶室八百余りが建ち並び、茶席は千五百席にも及んだとも言われている。
秀吉の茶室は組立て式の黄金の茶室で、秀吉のお手前を受けることが出来るくじとりが一般庶民にも許され、一番くじが秀吉、二番くじが千利休、三番くじが津田宗及であった。
身分の垣根を取り払い秀吉の突き抜けるようなO型の秀吉らしい突き抜けたような明るい性格が出ていていかにも楽しく華やかで今や天下太平なのだという演出が見事である。ところが慶長三年(1598)三月十五日、秀吉は醍醐寺の西大門から槍山(やりやま)(女人堂から山上に登る参道の途中の平地)までの参道の両側に畿内の近江、大和、山城、河内にあった約七百本の桜の木を移植させて、男性は秀吉、秀頼、前田利家の三人のみで、北政所、西の丸殿(淀殿)、松の丸殿、三の丸殿、加賀殿、前田利家の正室まつ、他は大名の妻、城に仕える女中など女性総勢千三百人を従えたという花見の宴席を設けた。女性には三着の着物を送り、二回の着替えを命じたという。

名護屋城天守台跡
現在のお金で約四十億円程かかったという世に名高い醍醐の花見である。この時、醍醐寺の周りは竹矢来で囲い、町衆は一人も寺内に入れさせず、暗殺計画を恐れた秀吉は五十町四方にわたって槍や鉄砲を持った警護衆を四方八方に配置しての花見であった。
北野大茶会に比べて随分の変わりようであるが、只々息子秀頼(六歳)に如何にして天下を相続せしむべきかを想うあまり秀吉が守勢に入った恐怖感がそうさせたのであろう。
秀吉は西国路を物々しい警備の中を通過し、関門海峡を渡って四月二十五日九州名護屋に着いた。名護屋は玄海灘に面した松浦郡の東松浦半島にあって、呼子に接する漁村で外海の波濤を避けるのに都合が良かった。
加藤清正を総指揮者として築造させた名護屋城は十七万㎡もの敷地の中に五層七階の天守を据え、外壁は真っ白な漆喰塗。飾り屋根の破風や、本瓦葺きの軒丸瓦などに金箔瓦を使って、松浦湾から見た天守の豪華さを意識して演出していた。
周辺には百三十以上もの大名の陣屋がひしめいており、約三十万の将兵が集められ、人口二〇万人を超える城下町を出現させた。今日残された城跡の残骸に壮大な意図を感じてか、青木月斗の「太閤が睨みし海の霞哉」の石碑が建てられている。
天正二十年(1593)四月十二日、釜山上陸以来わずか二十日余りで首都京(けい)城(じょう)(今のソウル)に入城した。六月十六日には平譲を占領との知らせが届いた。秀吉は明への侵攻もそう遠くはないであろうと、高をくくって在陣中は現地妻の広沢の局を連れて鯱鉾池で舟遊びを催したり、佐志山に窯を築き茶器を作らせたり、能楽に興じたりしていた。
しかし、秀吉は朝鮮に渡海出来ずに足止めを食った。明の進軍と共に戦いの潮目が変わっていた。海戦では脇坂安冶(わきさかやすはる)や藤堂(とうどう)高虎(たかとら)や加藤(かとう)嘉(よし)明(あき)が指揮を執り、九鬼水軍(九鬼嘉隆)を戦力の核としていたが、各藩の寄り合い部隊であったため指揮統制が執れていなかった。秀吉は毛利の小早川水軍には敢えて水軍としての役割を与えていなかった。
海との関わりという点で脇坂安冶(わきさかやすはる)や藤堂(とうどう)高虎(たかとら)や加藤(かとう)嘉(よし)明(あき)より、無論海域の地形、海流、潮の干満などを熟知して朝鮮水軍を統率していた戦略家の李舜臣(イスンシン)との対戦では、秀吉側は明らかに抗戦の態勢に終始せざるを得なかった。
総矢倉形式の日本水軍の軍船である安宅船は攻撃力・防御力などに優れている面もあるが、船全が亀のように頑丈な堅板で覆われ、その両側に戦闘用の穴を開けた砲艦で、甲板は敵が飛び乗れないように鉄板を葺いて鉄錐を打っていた朝鮮水軍の誇る亀甲船の反撃に手も足も出ずに敗北を重ねていった。
制海権を奪い返され、朝鮮半島への武器や食料の補給が困難となり、完全に当初の勢いが止まった。こんなことも見込んで日本最大の海賊と言われた村上海賊の大将能島村上家の村上武吉、元吉親子をいろいろな懐柔策を弄して味方に引き入れようと調略を企てて来たが、武吉はどうしても秀吉に靡(なび)こうとはしなかった。秀吉にも意地があり、敢えて小早川水軍を前面に押し出さなかったが、八方の敵をも対峙するという村上武吉がこの戦いに加わっておれば形勢は違っていたはずであろうと秀吉は内心では苦々しく思っていた。
そうした中、七月十八日、次船を利用して母大政所が重態に瀕したとの報告が秀吉の下に届けられた。秀吉は天正十六年(1588)、大政所の病気平癒を伏見稲荷大社(京都市伏見区深草)に祈願した際、ご祈祷料として楼門(現在入口に立つ楼門である)を建立した。
その際の秀吉の願文は「母の命を三年、だめなら二年、それがだめなら三十日の延命を」と、稲荷大社の御加護を祈願していた。大政所の体力の衰えは以前から秀吉の頭痛の種であった。急遽、秀吉は大坂に引き返すことにした。とるべきものもとらずに豊前小倉から船に乗った。
七月十九日朝、帰りを急いでいた秀吉が乗る御座船日本丸が暗礁に乗り上げた。
場所は船乗り達が恐れている関門海峡の潮の流れの激しい大里(だいり)の沖の死ノ瀬(篠瀬)と呼ばれる難所であった。御座船の船底が砕け一気に大量の海水が船の中に流入し、秀吉は命からがらやっとの思いで小舟に乗り換えることが出来て助け出された。
ここは狭い関門海峡に玄海灘の押し潮と周防灘からの戻り潮がぶつかり合う事で、十ノットとも言われる速い海流が大きな渦潮を作り出し、どんな大船といえどもここに突入してしまうと左右に大きく船は傾き、舵の効きが全く効かなくなってしまうという危険な場所であった。その上この辺りには露岩や暗礁や浅瀬があってここを通過するには相当の技量を要した。
座礁した日本丸の船頭をしていた石井与次兵衛は後にその責任をとって切腹して果てているが、この石井与次兵衛が天正五年(1577)三月十三日に航海の安全祈願にと奉納した騄(りょく)毛(げ)(黒・雄馬)と戧(そう)毛(げ)(白・雌馬)の二枚の絵馬が尾道市の浄土寺に残されている。(現在この絵馬は浄土寺宝物殿に収納されている)黒の雄馬は首を上げ、白の雌馬は首を伏せて共に切杭に繋がれた綱を力一杯引っ張っている姿を、抑揚ある鋭い描線や隈取り(遠近や凸凹を表すために色をぼかす技法)を用いて立体感や力強さを見事に表現している。
この二頭が夜な夜な額を抜け出して浄土寺の本堂内を駆け回ると噂になり、綱を後で書き添えたとの話も残っているほど力感のある絵馬である。
播州明石郡船上(ふなげ)(兵庫県明石市船上町)の住人であった石井与次兵衛(明石与次兵衛とも)は播州沖一帯に勢力を張っていた播州海賊の一人であったが、天正八年(1580)頃、秀吉の中国進出に伴い、その幕下に加わり、秀吉の四国出兵の時も島津攻めの時も参陣した事で地位も上がり、秀吉の信頼も勝ち得ていた。
尾道の浄土寺の観音信仰の霊験のあらたかさが遠く明石にまで轟いていることからも当時の瀬戸内海の海上交通の繋がりと、尾道の港と町の繁栄振りも伺い知ることが出来る。
長崎出島から江戸に向ったシーボルトは「与次兵衛瀬の碑」としてこの死の瀬の状況の絵を描かせている。現在北九州市門司区の和布刈(めかり)公園には元々は細川忠興が建てたと言われている与次兵衛の慰霊碑が昭和三十年に海難守護神として再建されている。

柳水井戸跡(尾道市長江)
海路の方が早いが、急いでいた復路も秀吉は陸路を採った。既に秀吉は海賊禁止令を出して村上海賊を始め瀬戸内海の水軍・海賊も管理下に置いていたというものの瀬戸内海には未だ秀吉に恨みを持つ海賊の残党が徒党を組んで何時襲ってくるとも知れなかった。
瀬戸内海の航行だけでなく、海戦となれば潮の流れや岩礁や暗礁等の瀬戸内海の海を精通している方が俄然有利であり、さすがの秀吉もこれを恐れた。
秀吉は九州肥前の本営から深江、名島、芦屋、長門、山中、花岡、小方(おがた)(大竹)、広島、西条、三原と宿泊して尾道に着いた。
尾道では本陣の笠岡屋(小川家)にその日の宿を取った。戦国武将毛利の御用商人であった笠岡屋、大西屋(渋谷家)、泉屋(葛西家)を年行司等の役に付け、彼等の商売のネットワークを利用して、町を自主的に管理させていた。天正十六年(1588)七月、秀吉が出した海賊取締令である「海で自由に生きてきた者達の調査」や「海賊をしない旨の誓約書の提出」等の実務も彼らによって取り纏められていた。
「尾道志稿」(尾道の豪商亀山士綱が著わした文献史料)によると文化十三年(1816)の笠岡屋は現在の尾道の本通りから米場通りまで続く大構えで、秀吉が着座したという「御座の間」が残っており、上段、上々段の間には狩野永徳の襖絵もあったと書かれている。
江戸時代には石見銀山から尾道に運ばれてきた銀鉱石は一旦この笠岡屋の蔵に運び込まれ、室津に向けて出帆する船に積み込むまでここで厳重に保管されていた。現在も江戸時代の屋敷蔵の基礎の石積が路地に沿って残されている。
家主は違うが笠岡屋の屋敷で使われていたという太い梁が、本通りに面した屋敷跡地にあるお宅の玄関入口にモニュメントとして使われている。

豊国神社唐門(京都市東山区茶屋町)
笠岡屋二代目当主・小川又左衛門は秀吉に長江(尾道市長江一丁目)に湧く当時尾道で最も美味であったと言う清水を汲んで来て、その水で茶を振舞ったと伝えられている。その井戸は後年「柳(りゅう)水(すい)」と名づけられており、この「柳水」の井戸跡には頼山陽の高弟であった宮原節庵の筆になる「柳水」の由緒書(銘板・石材)が取り付けられている。
由緒書の文字は長年の風雨に当たって殆んど読めなくなっているが、「文禄の役の際、肥前名護屋城にいた太閤が東上するに及んで、尾道の小川某なる者から接待を受けた際、この美味しい井戸の水を飲食に使った。
そのような 事があった事を後の人に知ってもらうために記す」と言った意味のことが書かれている。(この由緒書は幕末の三原の学者宇都宮(うつのみや)龍山(りゅうざん)によるとの説もある) 現在もこの湧き水は飲料水として用いることは出来ないが、こんこんと湧いて出ている。
翌朝、小川又左衛門は秀吉一行の警備を兼ねて毛利の所領の東の境であった神辺まで随行して見送った。この笠岡屋の丁寧な歓待に気をよくした秀吉は、別れ際、謝礼の品物を又左衛門に手渡しただけでなく、お供の者達にまで銀銭を自ら手渡して謝意を表した。
天下人から手渡されたお供の者達は天にも昇る心地がしたことであろう。又、その日又左衛門が乗ってきた馬を秀吉は大いに気に入って是非にと所望したので、又左衛門はその馬も秀吉に献上したという。
その後、秀吉は矢掛、岡山、赤穂、明石と宿をとって帰京した。本復を念じていたが、願いもむなしく既に母大政所は聚楽第で亡くなっていた。
せめて息を引き取る時ぐらい傍にいたかったと、母親想いの秀吉だけにその場で動転してしまうほどの衝撃であった。
秀吉の身を案じて朝鮮への渡海をやめるよう母に懇願され、秀吉はそれを無碍(むげ)には出来ず、出兵を一年延期していたほどであった。深い悲しみの中葬儀は大徳寺で執り行われた。
その後、朝鮮での戦いは小早川隆景等の活躍により明との直接講和交渉という運びとなっていたが、秀吉は明帝からの勅書「爾を封じて日本国王と為す」との書状に激怒して勅使を追い返し講和は決裂した。もはや後には引けない秀吉は慶長二年十月一日、朝鮮南四道を奪うことを目的として、再び名護屋に向け出発した。慶長の役である。
こうして又、約十四万もの軍が再び海を渡ることとなった。もともと秀吉は明国に出兵するのに当たって朝鮮国を先導役に立ててとも考えていたが、明国を宗主と仰ぐ朝鮮国が明国への道案内をする事等考えられなかった。
やはり当時秀吉や周りの者の国際感覚や洞察力は乏しかった。この時期の「毛利文書」には秀吉から毛利輝元への「秀吉朱印状」として慶長二年(1597)十月五日付で輝元から備後の畳表千帖と銘酒(酒樽十挺)を贈った謝辞と「朝鮮遠征も至極順調に進んでいるから貴殿までが朝鮮に出掛ける必要には及ばぬ」との書状が残されており、秀吉は戦局をまだまだ楽観的に見ていて、戦意は旺盛なものがあることが分かる。
朝鮮の人々からは「壬辰・丁酉の倭乱」と呼ばれたこの侵略戦争によって結果的に豊臣政権の屋台骨をゆるがせただけでなく、自身も寿命を縮めて慶長三年(1598)九月十八日伏見城で亡くなった。享年六十三歳であった。秀吉の死によって遠征軍は四分五裂の状態となって引き上げて来ることになった。
秀吉の遺体は京都東山の阿弥陀ケ峰に葬られ、翌年には壮大な社殿がその山腹に創建され、豊国(とよくみ)大明神(だいみょうじん)の神号を賜っている。
神となった秀吉の豊国神社の豪華な唐門は伏見城の遺構と伝えられていて国宝であるが、この神社の東側に東大寺をも凌ぐと言われていた巨大な大仏殿は現在雑草の中に礎石だけが虚しく残されている。
この大仏殿を始め、名護屋城、聚楽第、大坂城、伏見城と秀吉が心血を注いだ豪華壮麗な建造物は全て現存していない。天下人までに上り詰めた華やかな彼の人生の儚(はかな)さが伝わってくる。「露と落ち 露と消えにし我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢」と秀吉の辞世の句は言い得て妙である。
一方、「木下家」に伝わる「秀吉事記」では「露とちり 雫(しずく)と消ゆる世の中に 何とのこれる心なるらむ」との秀吉の辞世の句とされるものが残されている。
「人生は儚(はかな)いものであるが、もう少し長らえる事が出来たなら、もっと叶えたい事があったのに心残りで残念で堪らない」と、余所行きではない生の声で一大英雄秀吉の無念さが直に伝わってくるようで憐れをさそう。
伝承によれば、文禄慶長の役に水(か)主(こ)として従軍した尾道の漁業関係者は約六十人で、このうち戦病死した者は十七人であると言われている。
秀吉がその遺族を憐み、生活を保障するため、「晩寄(ばんよ)り」「晩選(ばんよ)り」(獲った魚を市場や魚屋を介さず市内至る所の街路で直接販売する権利)と言うお墨付きを交付したことから、今も尾道の町中では「晩寄りさん」と呼ばれている女性達が手押し車を使って露店(路上)で鮮魚を商う特有の行商風景が見られる。
林芙美子の小説「放浪記」には
「「ばんよりはいりゃせんかア」と魚屋が、平べったいたらいを頭に乗せて呼売りして歩いている。夜釣りの魚を晩(ばん)選(よ)りといって漁師町から女衆が売りに来るのだ。」とある。同じく林芙美子の小説「風琴と魚の町」にもその情景が書かれている。
「女衆がねじった手ぬぐいを頭の上に置き、魚を入れた平べったいたらい(荷ない桶)をその上に乗せて魚を売り歩いていた」と。
注3、天正十三年(1585)六月、小早川隆景は来島通総を先頭に立てて四国本土に攻め入り、八月には河野家の本拠湯築城を包囲した。城主河野通直も大勢を察して城を開き、隆景に降った。
しかし、隆景の口添えにもかかわらず、河野家の所領は没収されて、第七代孝霊天皇(第三皇子は吉備津彦命(桃太郎伝説)とも言われている)を祖とする河野家も、第五十九代の通直によって崩壊した。
河野家の再興を秀吉に取りなす事を約束してくれていた隆景が筑前の名島に転封され、結果的に伊予の最期の大守という事になった通直は湯築城を出て備後の竹原長生寺に身を寄せた。病身の通直は病が癒えないまま天正十五年(1587)遂に帰らぬ人となった。
享年二十四歳であった。竹原の長生寺は隆景がこの通直の為に寺領二百石を寄進して建てた真言宗の寺である。角折敷三文字の本堂鬼瓦の河野家の紋が戦国の世の習いとは言え哀れを誘う。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット