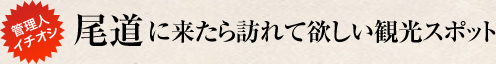![]()
平安時代都(みやこ)では華麗なる王朝文化の花が咲いていた。

貴船神社(京都市左京区鞍馬貴船町)
その中にあって優れた宮廷歌人でもあった和泉式部は別れた初恋の人である陸奥守橘(たちばなの)道(みち)貞(さだ)の事がどうしても諦めきれず、道貞がもう一度自分の方を振り向いてくれるようにと、すがる思いで京都洛北の貴船神社にお参りに出掛けた。
その時、御手洗川(貴船川)に飛び交う蛍の美しい風情を見て、「もの思へは 沢の蛍もわが身より あくがれ出(い)ずる魂(たま)かとぞ見る」(あまりあなたのことを思って悩んでいたら沢に飛ぶ蛍はまるで私の体から抜け出した魂(たましい)ではないか、身を燃やして生き、最後は燃え尽きて死ぬ定めの私自身ではないかと思えてきてなんだか悲しくなってしまいます)という歌が、自然に口をついて出た。
すると貴船の神様が「おくやまに たぎて落つる滝つ瀬の 玉ちるばかり物なおもひそ」(貴船の山奥にある滝をまるで自分の涙が集まって流れているように思ったり、飛び散っている水滴をあたかも砕け散る自分の魂のような気がしているだなんて、そのうちにきっと良い事もあるだろうから、そんなに思い詰めるものではない)という歌が返ってきたという話が後捨遺和歌集に収録されている。
貴船が「気生根」と転じられる事から、昔からここが「気力が生じる根源地」であるとされる裏付けにもなっているのであろう。

貴船神社「蛍岩」
又、毎年六月中頃からこの付近の水辺には青白い光を放つ蛍の乱舞が見られる事から、蛍の名所の一つとなっており、ここにある大きな岩を「蛍岩」と呼んでいる。
そして御手洗川に沿って本殿までの道は誰が名付けたのか「恋の道」と呼ばれている。
和泉式部の父は下級貴族であった越前守大江雅致(おおえまさむね)、母は平保衡(たいらのやすひら)の娘で太(たい)皇太后(こうたいこう)(天子の祖母)昌子(しょうし)の乳母であった人である。
成長するに従って式部は美しさと才能を兼ね備え、鋭い感受性を持った女性へと成長し、誰からも注目される存在になっていった。
やがて式部は父よりも身分の高い和泉守橘(たちばな)道(みち)貞(さだ)に輿入れをすることになり、式部は「和泉式部」と呼ばれるようになった。
そして、母譲りで歌才のある娘小式部(こしきぶの)内侍(ないし)と、もう一人男子が生まれた。ところがそんな幸せの絶頂期にありながら、夫橘道貞が国司となって地方へ単身赴任したため式部は京に残ることとなった。
一人京に残った式部はやるせない思いを歌を作る事で紛わしていた。そんな歌が朝廷内の公家達に知られる事となって、中でも冷泉天皇の第三皇子である弾正宮為(ため)尊(たか)親王は妻帯者でありながら式部に夢中となり夜な夜な通う仲となっていった。
親王二十二歳、式部二十六、七歳の頃のことである。面子を潰された道貞は激怒して式部を離縁した。父からもあってはならない不祥事であると式部は勘当された。ところがその為尊親王が一年後に亡くなってしまう。
その喪に服していた期間にあろうことか今度は、兄の面影を残している容姿の弟の第四皇子である帥宮(そち野みや)敦(あつ)道(みち)親王の猛烈なプロポーズに負けて再び式部は恋に落ちてしまう。
しかし再び災(わざわ)いが続き、彼もまた五年後に突然身罷ってしまう。「和泉式部日記」はこの敦道親王との恋の顛末を記したものである。
そんなことがあってなかなか立ち上がれずに落ち込んでいた式部に時の権力者藤原道長から宮仕えを勧められた。
道長の娘・上東門(じょうとうもん)院彰子(しょうし)(一条天皇の中宮)が式部の歌才を惜しんで出仕を是非にと懇望していたとも言われているが、これは道長の策略で長男道隆の娘である中宮定子(ていし)(一帝二后であった)には清少納言が仕えていて、彰子の周りにそれ以上の宮廷サロンを作って彰子側に一条天皇の取り込みを図ったのである。
式部は道長の要請を受けて寛弘五年(1008)、娘の子式部と共に中宮彰子の女官として出仕した。こうして彰子の周りには紫式部、赤染衛門等と共に華やかな宮廷サロンが築かれていくことになった。
長和二年(1013)この宮仕えが契機となって式部は道長の家司(いえのつかさ)であった藤原(平井)保(やす)昌(まさ)と再婚をすることになった。
保昌は道長の信頼は厚かったが、武骨で年齢も五十を過ぎており、敦道親王への思いが立ちきれないでいる式部としては必ずしも望んでいる相手ではなかった。それでも式部は前轍を踏まないようにと夫の任地であった丹後国へ一緒に下っていった。
暫くして今度は運命の悪戯か一人娘の小式部内(こしきぶのない)侍(し)が産後幼い子供を残して亡くなってしまう。
万寿二年(1025)の事であった。当時政情は不安定な上に都は不衛生な環境から疫病が蔓延していて早世する事も多く決して珍しい事ではなかった。しかし母の式部の悲しみは大きかった。
娘の孫達を見て「とどめおきて 誰(だれ)を哀れと思うらむ 子はまさりけり 子にまさむらむ」(娘は親の私や小さな子供を残して亡くなってしまった。
あの娘(こ)は何と言っても親の私の事以上に子供の事が気がかりであるに違いない、残していく子供のことほどつらいことはないだろう。私だって娘が亡くなったことがこんなに悔しくて哀しいのだから) 、「子は死して たどりゆくらん死出の旅 道しれずとて帰りこよかし」(あなたは一人でなんか死出の旅なんか行けやしない。あなたは昔からずーとそんな子だった。
きっと途中で道に迷うだろう。道に迷うぐらいなら一刻も早く私の所に帰って来て頂戴)と母親として娘を亡くした深い嘆きが伝わって来る。
小倉百人一首では小式部が心無い公達から丹後にいる母にアドバイスをもらったのではとからかわれた時、とんでもないと切り返した歌である「大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立」(大江山を越えて、近くの生野へと向かう道さえ行った事が無いのに、まして母のいる遠い天の橋立の地を踏んだことも無く、まだ母の文(ふみ)(手紙)も見た事もありません)が母の歌と共に収められている。
世の無常を感じた式部は播磨国書写山圓教寺に性空上人を訪ねた。
上人は都では心の救済者として知れ渡っていた。生憎上人にはお会いする事は出来なかったが「暗きより暗き道にぞ入りぬべき 遥かに照らせ 山の端の月」(私は煩悩のせいで歩いてきた暗闇の道から、それ以上の暗く深い迷いの道へと入って行ってしまいそうです。
一人で苦しんでも悩んでも解決出来ません。相談する人もいません。山の端に出た月が夜の闇を照らすように、上人様、私の進むべき道をお示し下さい。御慈悲ですから)との歌を書き残して虚しく山を下りた。
当時女人には極楽往生は出来ないものとされていたが、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば女人でも極楽往生が出来るとの性空上人の教えから、出家して「専意法尼」という戒名を授かり、ひたすら念仏三昧に明け暮れた末、誓願寺誠心院(しょうしんいん)で亡くなった。
テキスト ボックス式部が初恋の人である橘道貞(諸説あり)と別れた後、忘れかねて詠んだとされる和泉式部集、後拾遺集の「黒髪の乱れも知らずうち臥せばまずかきやりし人ぞ恋しき」(黒髪が乱れてしまっているのも気づかないほど気を失っている私の黒髪をそっとかき上げてくれたあの人の優しさがたまらなく恋しいのです)のように激しく情熱的な恋は女性にとっていつの時代も憧れなのであろう。
又、藤原定家は数ある式部の歌の中から小倉百人一首に「あらざらむ この世のほかの思い出に いまひとたびの 逢うこともがな」(私の命はもう長くない。あの世へ旅立つ前の思い出に、もう一度恋しかったあの人に逢いたい)との歌を選んでおり、式部の代表作のようになっているが、死を前にしてもなお恋しい人(橘道貞)へ愛の叫びとなっており、その業の深さに哀れさ・切なさを感じる。
京で浮名を流したことから、式部が落とした扇を拾った藤原道長が「うかれ女(め)のあふ(おう)ぎ」(浮かれ(うかれ)女(め))と悪戯書きをしたほどスキャンダラスな女性というネガティブな捉え方もされている。
同時代の紫式部も「口先ですらすらと即座に歌が詠める」と式部の歌の魅力・実力を認めながらも、多情で浮気な女と酷評しているが、それでも式部の瑞々しい情感に溢れた歌は、時代を超えて今なお私達の心に響いてくる。

和泉式部墓所(誠心院)
(京都市中京区新京極通六角下ル)
毎年七月十七日、京都の祇園祭で山鉾巡行が行われるが、その中の「山」の一つ「保(ほう)昌山(しょうやま)」は再婚した丹後守の平井(ひらい)保(やす)昌(まさ)と和泉式部の恋物語に材を得たもので、保昌が式部の無茶な求めに応じて御所に忍び込んで紫宸殿の紅梅を手折(たお)ってくるという話を形にあらわしている。
その甲斐あって目出度く二人が恋を実らせたという山の故事にちなみ、宵山では「縁結び」の御守りが授与されており、沢山の人が買い求めている。(平井保昌は源頼光酒呑童子退治の図にも頼光四天王プラスワンとして出て来る)
京都の新京極通りと言えば、修学旅行の生徒の観光スポットの一つであるが、蛸薬師通りを上ったところにその賑わいとは無縁であるかのように、ひっそりとした佇まいの誠心院(しょうしんいん)という寺がある。
式部はこの寺で出家し、往生を遂げたとされていて、彼女の墓として高さ五メートルほどの大きな石造りの宝篋印塔(ほうきょういんとう)が建っている。
本堂内には式部の像も安置されている。境内では式部のファンの方はもちろん、ここがあの式部の墓なんだ、新京極との賑わいとの落差が大きすぎてこんなところにと意外な顔をしながらお参りしている方をよく見かける。
誠心院では命日とされる三月二十一日に毎年「和泉式部忌」が行われている。
尾道には和泉式部伝説がある。長徳四年(994)和泉式部が藤原保昌と共に船で厳島神社に参拝に向かっていた途中、布刈(めかり)の瀬戸でにわかに海上が荒れ始め、乗っていた船が難破しそうになった。
式部は観音菩薩像を胸に抱きしめ必死にその暴風雨が治まってくれることを祈ったところ、なんとか無事に向島の古江(こえ)の浜(尾道市向東町古江浜)に漂着することが出来た。これに感謝して式部は、守り本尊として持っていた観音像を安置して、西金寺(尾道市向東町歌)を草創したと伝えられている。
現在の西金寺の鐘楼門をくぐった左側には再建した観音堂があるが、残念ながら式部が祈願したと言われる聖観世音菩薩が安置されていたという観音堂は江戸時代に焼失しまって現存はしていない。その観音堂の脇を抜け、西側の裏山の墓所の中の細い山道を登って行くと、既にすっかり風化してしまっているが、式部の墓とされている高さ一メートルばかりの無銘の五輪塔が東の方を向いてひっそりと建っている。
一坪程の墓所(はかしょ)は関係者の方が手入れされているのかよく掃除が行き届いている。式部はこの西金寺で死没したと伝承されている。
又、式部が漂着したという古江(こえ)の浜は、地元の人が金毘羅さんと呼んでいる神社になっていて、大正十一年(1922)に建てられたという「和泉式部手植下り松碑」との石碑もある。
残念ながらその下り松自体は既に枯木となってしまっているが、当時この松の枝は四方に伸びて数十歩を覆ったと伝えられていて、平安後期の女流歌人相模(さがみ)も「萬代のかげをならべて鶴の住む古江の浦は松そこたかき」とこの松を詠んだという歌を残している。
神社の境内には古びた舞殿と笠木の上に風で飛ばされないよう漆喰で固められた瓦が乗せてある珍しい鳥居や、海中から引き上げられたと言う自然石に水穴をくり抜いただけの手水鉢などがある。
前方に堤防が出来ていて海とは区切られてしまっているが、式部が漂着した当時はこのあたりは漣が寄せては返す白砂青松の海岸線が広がっていたのであろうと妙にノスタルジックな気分にさせられてしまう。
しかし前面は埋立てられて一部は道路にもなっており、松は枯れて雑木種に生え変わってしまっており、その周りの大きな変化に現実に引き戻されてしまう。

和泉式部供養塔(西金寺)
向東町歌の曹洞宗西金寺は比丘尼による仏教熊野信仰の布教拠点の一つで、京都市上京区六軒町あたりにあったと言われている護念寺を開基したという月(げつ)舟(しゅう)和尚、その月舟和尚と月舟和尚の後継者であった比丘尼・月(げっ)浦(ぽ)の冥福を祈る為、比丘尼覚(かく)照(しょう)は京都から下向して来て西金寺の住職となっていた。
その覚(かく)照(しょう)が西金寺に縁の繋がる比丘尼達十数名を集め、自身の両親、祖母も含め、死者の霊魂が一日でも早く成仏するように、又、神仏の恩恵が衆生に与えられん事を願って写経し、奉納したという「反古紙経」が、安芸の宮島の厳島神社で発見された。
この「反古紙経」は、当時は大変貴重であった紙(連歌懐紙や公私の古文書など)を糊で継ぎ合わせて巻物にし、その裏面に写経したもので、その背文書に書かれてあった古文書(1288~1330)から、鎌倉時代向島に住んでいた人々の暮らしぶりの一部を知る事となった。
その古文書には、酒屋一同(?)から提出された年貢減免嘆願書や京都の東寺の領地であった弓削(ゆげ)島(じま)か因島の百姓が、年貢を踏み倒したという話、歌島の公文職兼預所(あずかりどころ)(年貢などを管理する職名)に任命されていた知(ち)栄(えい)という人物が借金をした話、京都に住んでいた知栄の娘が法要を依頼した等が書かれているが、残念ながら和泉式部に直接結びつく資料は見つかっていない。
和泉式部についての説話や供養墓は全国にいくつも残っているようであるが、中国地方では賀茂郡豊栄町、高田郡美土里(みどり)町に伝説が残っており、又「砂の器」で有名になった島根県の奥出雲の亀(かめ)嵩(だか)駅の近くにも祠が建っている。
向島に残るこの和泉式部伝説は向島が当時、大炊寮領(皇室御料地)として、在京の三条の中原氏(大炊領頭)の支配下のもとで経済的発展を遂げていく中で、中央の貴族の文化が少なからず流れ込み、とりわけ歌好きな熊野信仰の比丘尼によって、京文化に心引かれ、和泉式部の宮中生活や華やかな恋の遍歴、又、悲劇の主人公として自分に重ね合合わせる事で、たとえ和泉式部の様に煩悩まみれでも信仰さえすれば極楽往生が出来る事を語り継いで行くうちに伝説として定着してきたものなのであろう。
民俗学の第一人者である柳田國男氏も「中世にかけて京都の誓願寺派(熊野信仰)の比丘尼達が和泉式部の伝説を語り歩いていた」と語っておられる。
向島のことを昔は歌島、歌の島と呼び、西光寺がある場所も「歌」という地名である。又、向島の北側にある小島(昭和七年から陸続きとなったが)を向島の歌島に対して小歌島(現在は岡島)と呼んでいたこともあった。
このような呼ばれ方をされているからには比丘尼達が式部の伝説を語り継いでいたからではないかというだけでなく、もっと別の理由があるのではないか、今後更に新しい和泉式部に関わる資料が発見される事が待たれる。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット