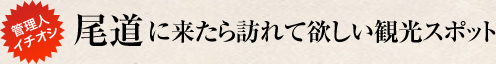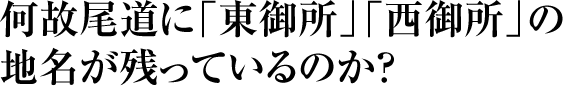
地元の旬刊誌備(注2)後経済レポートの「尾道の謎」という連載で、尾道に「御所」という地名があることこそ「謎」であるとのレポートを瀬戸康男氏が発表されていた。
三年前に京都から尾道に引っ越してきた私は、京都にいた時「御所」という言葉を都が東京に奠都されるまでは「天皇さんが住んでおられた場所」という程度で、特に深い意味など考えず日常的に当たり前に使っていたのであるが、瀬戸氏は「御所とは天皇が住まわれる場所であって天皇、皇族以外に使うことが出来ない。

京都御所 建礼門
あの足利義満の「花の御所」でさえ天皇に許可をもらって使っていたという。天皇と関係する所が尊敬を込めて「御所」と呼ばれたのであるからあだやおろそかに「御所」と名乗ることは出来ない」と述べておられた。
しからば、何故尾道に「東御所」「西御所」の地名が残っているのか。「尾道」と「御所」一体どんな関係があるのだろうか。
尾道の郷土史家財間八郎氏はその著書「落葉かご」の中で「師(注1もろ)守記(もりき)には足利尊氏の時代である貞和元年(1345)の頃、既に「備後御所崎」という地名が見られる。
しかし、ここでいう「御所」とか「御所崎」は持光寺山の南端が海へ突き出たところを御所崎と呼んだのだから、現在の土堂町の一角をさしたものである。
又、安永三年(1774)の安永の絵屏風(浄土寺保有)などで見ると、現在の御所町は全く海の中である。しかも、その頃、巌通川と栗原川から流出する土砂の量は莫大なもので、港湾を生命線としてきた尾道にとって港としての使命を果たすことが出来なくなってきた。
そこで、明治二十年(1887)、流出した土砂によって埋没した栗原沖をさらえ、東・西御所及びその東部の海岸を埋め立てた」と現在の御所町のなりたちについて述べられているが、何故「御所」という名前が付いたのかの理由については追究されておられない。
宝土寺(東土堂町)の古文書には「大日本国備後州御調郡栗原保尾道之浦御所崎宝土寺信心大檀那橘信吉 長享三巳酉年仲」とあり、応仁の乱終結後の長享三年(1489)の頃には「尾道の御所崎」という地名が書き記されている。
又、「栗原保」ということから、この辺りには朝廷の所領である「大炊寮」があったことが分かる。
新修尾道市史で青木茂氏は現在の御所町が新しい埋立地であることを承知された上で「南北朝時代栗原、吉和、向島、御所崎は朝廷の荘園であった。これらの荘園からは朝廷へ熟食米(廻米)が京都に送られていた。
そうすると、御所の食糧を扱う担当の在京の中原氏に代わって、現地責任者である中原氏の荘司が此の辺りのどこかに定住してこの采配をしていたはずである。京都熟食米(廻米)を京都に送るのにあたって積出港が必要となるが、この積出の地域を想定してみると、栗原にも吉和にも適当な場所がない。
その港としては「御所の地名」あたりが格好の場所になる。そこでここにその業務を扱う下級役人が駐在していたことから、その居宅を土地の人は尊称して「御所」と言った。この地名がそのまま現在に残って「御所町」となっているのではないか」と私的仮設をたてておられる。
頼杏坪著作による「藝藩通志」(巻三十三)には「祠廟」の一つとして「荒神社」があり、それには「土堂町にあり、里人相傳ふ、此社、舎人親王をまつる、故に此地を御所と呼ぶ、荒神は皇神の訛ならんと、按るに、親王は盡敬崇道皇帝と追號すれば、御所と稱する謂なきにあらず」とある。
瀬戸氏は亀山志綱筆の尾道の歴史書「尾道志稿」(文政八年(1825))から「土堂町の荒神宮は古き鎮座のよし、其の年代分かりがたし。古老曰く、当社は舎人親王を祭れり、故に此のあたりは御所と唱えるよし。
されは神号も古代は皇神と書きしを後、荒神にかへしならん。蓋、以前は僅の小祠なりし由、地面を築上、今の社を造営せしは百年前のことなり」とあることから、荒神宮ではなく皇神宮であり、今の荒神堂小路は皇神宮への参道であったと「藝藩通志」と同じような説をとっておられる。
又、瀬戸氏はこの尾道で「御所」の地名を使ったということは、天皇の在所(ざいしょ)であり、大同元年(806)に創建された艮(うしとら)神社(じんじゃ)(尾道市長江一丁目)は鬼門を守る神社として、ほぼ同じ頃、この「御所」に舎人親王を祭神とする皇神社(皇神宮)が出来たのではないか」と推論されている。
「兎に角、舎人親王の神社が江戸時代の後期まで残っていた。舎人親王を神として祀る神社は全国でも極めて稀である。であるから舎人親王がこの尾道に在していたと考えるのが道理なのだが、残念ながらそのような資料は見つからなかった」と述べられておられる。
確かに、荒神堂の地名の由来となった「荒神宮」は江戸後期の文政の町絵図では本通りから小路へ下る角地、現在は八百屋さんが位置している場所に見える。艮神社の南西の方角、裏鬼門に位置している。
現在はこのお宮さんは艮神社の境内に移設されているとされているが、艮神社の御祭神は火の神・竈の神としての荒神様と、素戔嗚命の神が合祀されているばかりで、残念ながら舎人親王はお祀りされていない。

尾道市「御所」地名表示
さらに荒神堂小路の更に南西側にある「からさわ」さんの辺りを、古老は「御所浜」と呼んでいるものの、「御所町」は尾道駅の西側でこの辺りは「御所町」とはなっていない。
艮神社という名の神社は主に備後地方の各地に存在していて、お隣の福山市では福山城の北東の方角に位置していてお城を守っている。
尾道の土堂にあった荒神宮の北東に位置する艮神社、その御祭神は舎人親王であるとされればストーリーは完結するのであるが、陰陽五行説の解釈の仕方とか、備後地方にだけの何か特別の謂れがあるのかもしれない。
歴史書によると舎人親王は養老四年(720)に日本書記を編纂して、日本で最初の学者として学問の神様とされており、天平五年(735)、六十歳のときに平城京で亡くなったとされている。
ちなみに、舎人親王をお祀りしている神社は全国的に見ても数少ないが、その一つが勝運と馬の神社として知られている京都伏見区深草にある藤森神社で、その東殿に天武天皇との二柱として御祭神とされている。天平宝字三年(759)、藤尾(伏見稲荷大社の社地)に建てられた藤尾社を元としており、この年には舎人天皇の御子息である大炊王が淳仁天皇として即位されている。
藤森神社の本殿には神功皇后、素戔鳴命ほか五神を御祭神としており、この神社は五月五日のかけ馬神事、武者人形を飾る端午の節句の発祥の地としても知られている。お稲荷さん(イネナリ)の社地に祀られていた舎人親王は五穀豊穣を祈る「大炊領」とも浅からぬ縁があったのかもしれない。
不知火海天草に浮かぶ島に「御所浦町」と呼ばれている地区がある。ここではあの壇ノ浦で非業の死を遂げたと言われている安徳天皇が九州の武将原田氏に導かれ、ここまで落ち延びて来て、この地で亡くなったのであるという。
源氏の追手を逃れるためか、「近衛殿」とだけ墓所に記されていて、墓石には特に何も刻まれていない。しかし島民によってここが安徳天皇の陵墓であると語り継がれている。
このように全国で「御所」という名で呼ばれている地域(奈良市・横須賀市・金沢市・長野市)には「大炊寮」からの説と「皇神宮」からの説とがあるが、尾道の「御所町」が「御所町」と呼ばれる由来はどうもはっきりしない。
注1 師守記(もろもりき)
南北朝時代の暦応二年(1339)から応安七年(1374)、公家の中原師守の日記である。中原氏は代々外記(律令制において朝廷組織の太政官に属し詔勅の草庵の添削や奏文の作成、儀式の執行などを司る部署)を世襲した家柄である。外記に就任する前は大炊頭にあり大炊寮領を統冶していた。大炊寮を中心とした出来事に関する記述も多い。
注2 大炊寮
煮炊きの文字から示されるように日本各地の所領地から宮中での飲食、とりわけ神仏へ奉られる供物や宴席の飲食等を管掌した部署。
注3 備後経済レポート
人・モノ・コトをつないで地域経済の活性化に貢献することをモットーに高いクオリティーの情報と紙面づくりに努められている地元の旬刊誌である。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット