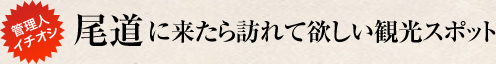![]()
瀬戸内海は「七里七島、五里五島、三里六島に一里百島」と言われている多島海で、百島の「百(もも)」という字が、「多くの数」と言う意味でモモ木、モモ島、モモ船、モモ夜などと用いられ、近くに田島、横島、賀島、向島、加島など「モモ(百)」島の一つとして考えれば当たらぬ地名でもないような気がする。(新修尾道市史) 又、島に桃の木が沢山あったことから「桃島」と書いている分かりやすい中世文書もある。
さらに、古くは潮が引くと二つの島になり磯島(五十(いそ)島(じま))と呼んでいたのであるが、土砂に埋まってしまって一つの島の形態になったので百島と呼ぶ様になったという説もある。
昭和三十年まで百島村は旧福山領に属していたが、尾道市に合併するのか、付近の島嶼を合併して町形式をとるのかを議論の末、尾道市に編入することになった。
千鳥が飛んでいる様な形をしたこの島は周囲約十六㎞の瀬戸内海に浮かぶ孤島で、現在五百人程が暮らしている。島の中には信号もコンビニも無い。

お弓取り神事
尾道駅前の桟橋からは備後商船の快速のフェリー「ニュー備後」で約二十分、フェリー「百風(ももかぜ)」では約四十分で百島の玄関口である福田港に入港することが出来る。
島の高台には百島八幡神社が島の産土神として鎮座しており、この百島八幡神社で毎年正月十一日に「お弓神事」という伝統行事が行われている。
この「お弓神事」の起源は、嘉吉元年(1441)の戦乱(嘉吉の乱)で足利軍に追われた赤松満祐の一族である七人衆(武田、村上、佐藤、藤田、宇根、堀川、稲葉)がここに流れ着き、住み着いて敵の襲撃に備えて弓の稽古をしていたことが始まりであると言い伝えられている。
又、この七人衆に赤松氏を加えて百島草分けの家として八軒衆と呼ばれる八戸もあって、前畑に移住したこの赤松氏等は南北朝時代の武将赤松則(のり)村(むら)(円心)子孫であると称し、播磨から逃げてこの島に定住したとの話もある。
しかし逃げて来ているのに、反乱の疑いをもたれる「赤松」を始めから名乗る事は無いだろうから、赤松氏は住み着いた初めの頃は七人衆で通し、落ちついて来てから八軒衆と言われるようになったとも考えられる。

お弓取り神事
応永三十五年(1428)室町幕府四代将軍足利義持(よしもち)は後継者を決めないまま死去した。嫡男であった五代将軍義量(よしがず)は十九歳で将軍に就任後まもなく早世しまった。
義持には他に男子はいなかった。そこで義満の猶子(ゆうし)で醍醐寺の座主三宝院(さんぽういん)満済(まんさい)は、将軍の候補者を仏門に入っていた義持の弟四人に絞り、くじ引きによる後継将軍選びに委ねる許可を取り付けた。
候補者は青蓮院の義(ぎ)円(えん)、大覚寺の義(ぎ)昭(しょう)、相国寺の永(えい)隆(りゅう)、そして梶井門跡三千院の義承(ぎしょう)の四人であった。そして正長元年(1428)、戦いの神様である石清水八幡宮でのくじ引きの結果、青蓮院の義円(義満の第二子)が引き当てられた。当初義円はいきなり還俗する事に気が進まなかった。
それでも将軍の地位に昇る事が八幡宮の神意にかなうことであると納得しこれに従った。足利義教(よしのり)三十五歳の事である。
室町幕府には機構として三管領四(さんかんれいし)識(しき)があった。管領とは足利将軍を補佐するもので、細川氏・斯波氏・畠山氏が交代でこれに当たっていた。
同じく四識は侍所の長官を務める赤松・一色・山名・京極の四家が交代で京都の警備と刑事裁判を担当していた。四代将軍義持はこれら有力守護大名の合議(宿老会議)の頂点に立つ存在であったが、実質的には将軍に代わって政(まつりごと)を動かしていた。
将軍職についた義教も当初はこれを踏襲して政治を行っていたが、しばらくすると持ち前の行政手腕を発揮し、将軍の権力を強化して幕府の権威を高める為の機構改革を断行した。まず独自の軍事力が必要であるとして、奉公衆と呼ばれる五千から一万人規模の将軍直轄の軍隊を整備した。合議制にもメスを入れ、合議に参加できる大名を自らが意のままに選べるよう変更した。
有力な守護大名の家督問題にも介入し、守護大名への支配力を高めていった。応永の乱で父義満に反逆した周防国の大内義弘(よしひろ)の子である持(もち)世(よ)に大内氏の十二代当主として家督を相続させ、九州で主導権争いを繰り広げていた渋川氏や少弐氏、大友氏を撃破させ、持世を九州探題とし、混乱していた九州を安定化させた。
持世はその後実力で周防・長門の守護となっている。又、土地争い等の裁定を最終的に将軍自らが決定する裁判システムを創った。さらに、永享六年(1434)かって義教が天台座主を務めていた比叡山延暦寺が幕府の統制に服さないとみるやこれを制圧した。
僧侶達は義教を非難して最澄(さいちょう)以来守ってきた根本中堂を炎上させ自害するという騒ぎとなった。又、東国の要であった鎌倉を守る副将軍ともいうべき関東公方(くぼう)足利持(もち)氏(うじ)が京都の政権に対して反抗的であると見るや、永享十年(1438)、足利持(もち)氏(うじ)を制圧、自害に追い込んだだけでなく、三人の子供までも殺害してしまった。(永享の乱) さらに途絶えていた日明貿易を復活させて傾き始めていた幕府の財政の立て直しを行った。そして、南朝の皇籍を剥奪し追放して南北朝問題を決着させている。
こうしたドラスチックな改革を進めていく上で、義教に異を唱える者や義教の機嫌を損じた公家や大名や僧侶、それを噂する庶民に至るまであらゆる階層に対して厳格な性格の義教によって容赦なく皆ことごとく粛清させられた。
このことを当時の後花園天皇の父でもあった伏見宮(ふしみのみや)貞(さだ)成(ふさ)王は、その日記「看聞(かんもん)御記(ぎょき)」に義教の政治を「万人恐怖」「薄氷之儀恐怖千万」と書き記している。義教は将軍の持つ権力による独裁政治によって人々を恐怖に陥れた。勿論、義教を取巻く人々は上辺だけは黙って従い取り繕いながらも内心は義教から遠ざかっていった。
この頃幕府の最長老格(侍所長官)で、播磨・備後・美作の三カ国の守護大名であった赤松(あかまつ)満祐(みつすけ)(PF・1)とは義教は将軍就任直後からお互いの潔癖症が災いしてか馬が合わなかった。
満祐は義教より二十歳以上も年上で、還暦をはるかに超えていた。義持が亡くなる前の年(1427)には義教は狡猾な満祐に対して腹を据えかね備後国の守護山名氏に満祐討伐を命じている。(PF・2)義教は満祐の事を「三尺入道」などと揶揄して見下すようになっていた。
永享十二年(1440)三月、満祐の弟義雅は義教の怒りに触れ、義雅の持っていた所領を全部召し上げ、義教はその大部分をおなじ赤松氏の庶流の赤松貞(さだ)村(むら)に与えた。家内の対立を煽る義教の巧妙、且つ冷静な策戦であった。
満祐は意を決してこの不公平を言上したが、無論義教は聞き入れる事はなかった。そんなことがあって、いずれ播磨の守護も満祐から貞村へ変更されるのではとの噂が囁かれていた。満祐はそうなることを恐れ、先手を打って赤松家では満祐が乱心したとして満祐を隠居させ、嫡男で十九歳の教(のり)康(やす)(満祐の子)を当主とした。
赤松家五輪塔嘉吉元年(1441)六月二十四日、教(のり)康(やす)は結城合戦の祝勝の宴として、「我が屋敷の池の鴨の子が沢山生まれたので是非その泳ぐ様を御覧になって頂きたい」と言上して義教を西洞院二条上ルにあった赤松邸に招いた。
この宴に相判した大名は管領(かんれい)の細川持之(もちゆき)(細川勝元の父)、畠山持(もち)永(なが)、山名持豊(宗全)、一色教(よし)親(ちか)、大内持世、京極高数(たかかず)、山名熙(ひろ)貴(たか)、細川持(もち)常(つね)、持(もち)春(はる)、赤松貞村、飛鳥井実(さね)雅(まさ)(義教の正室の兄)などであった。
義教は護衛を引きつれ申の刻(午後四時頃)に赤松屋敷に入った。最上段に義教が席に着くと早速酒盛りが始まり、舞台では笛、小鼓、大鼓等を持った囃子方に合わせて観世の猿楽(さるがく)の「高砂」が演じられた。庭の池では鴨達がいつもと違った華やかさに驚いて、せわしなく池の中を動き回っていた。
二番目の「清(きよ)経(つね)」が終わり、猿楽の三番の「鵜飼(うかい)」が演じられる頃には夕闇に篝火が赤々と燃え盛り客達はすっかりくつろいだ気分になっていた。そんな時突然、「馬が逃げたぞ」との叫び声が発せられ、邸内にいななきと蹄(ひづめ)の音が鳴響いた。と同時に出入り口の門扉が「ギィ・ギィ・ギィー・ドゥォーン」と軋んだ音を響かせながら閉ざされた。
義教は「何事ぞ」と周りの者に問うた。隣にいて猿楽に興じていた実(さね)雅(まさ)は「雷でも落ちたのでごじゃろう」と気にも留めなかった。
ところが、次の瞬間、義教の背後の襖が開け放たれるや、金屏風が蹴飛ばされ、抜刀した完全武装の赤松家の武者達が乱入してきた。そして、赤松家きっての剛の者と言われた安積(あづみ)行(ゆき)秀(ひで)によって一刀のもとに義教の首が切り落とされた。放たれた首は壇上中央にドスンと落ちた。残された胴からは血が噴き出して舞台は血の海となった。
目の前で起きた異常事態に同席していた者達は突然の出来事に何事が起こったのかと身体が硬直して動かなかった。
暫くして事の重大性が分ると狼狽(うろた)え逃げ惑った。将軍を警護するものと赤松家の武者達とが切り合いになったが、切りかかってくる赤松家の武者達に不意を襲われ、明らかに気持ちの上で遅れをとっていた。山名熙(ひろ)貴(たか)はその場で切り殺された。
細川持(もち)春(はる)は片腕を切り落とされ、京極高数も瀕死の重傷を負った。義教の後押しで大内家の家督を継いだ大内持(もち)世(よ)は奮戦するも酔いの回った身体ではさすがに力及ばず瀕死の重傷を負った。
実雅は後ろにあった赤松氏から将軍に献上された太刀を掴み取って身構えたが、恐ろしさのあまり切っ先が小刻みに揺れて止めることが出来ず、簡単に太刀を払い飛ばされ耳の辺りを切られて気絶した。赤松貞村は腰が抜けてほうほうの態で逃げ去った。

百島にある一隻五輪塔(赤松一族の墓?)
本来将軍を守るべき次席の高官であった管領細川持之は我が身可愛さで真先に逃げ出したので、(腰が抜けて立ち上がれなかったとも)それを見た他の大名達も我先に逃げ出そうとした。
そのため持之は後になって満祐と結託していたのではないかと非難されることになった。
ほどなく騒動が静まると、満祐は屋敷に火を放ち義教の首級を持って、悠々と領国の本拠地播磨の坂本城(兵庫県姫路市)に帰った。
「看聞御記」では「義教は自業自得である。このような将軍の犬死は古来聞いたことがない」と書き残している。
突然独裁者であった義教を失った幕府は機能不全に陥った。六月二十五日、管領細川持之は評定を開き、義教の嫡子八歳の千也(せんや)茶(ちゃ)丸(まる)(義勝)を次期将軍に決めたが、なかなか事態の真相が掴めず、少なからず赤松満祐に同情する者もいたため、すぐに幕府は赤松討伐軍を編成しきれなかった。
そこで細川持之は後花園天皇に赤松討伐の綸旨(りんじ)を申請し発行してもらった。このことは皮肉にも義教が行った将軍親政の政策の結果と言えないでもなかったが、管領細川持之の政治能力の欠如、合議による政治の破綻等、幕府の決定力の無さを浮き彫りにした。
征討の綸旨が下りた七月二十六日、細川持常、赤松貞村が摂津から赤松教康の軍の攻撃を開始した。
山名教清は伯耆から美作へ進軍した。八月中旬、赤松討伐軍の司令官たる山名持(もち)豊(とよ)(宗全)は但馬(たじま)・播磨国境の真弓峠に攻め込み、この方面を守る赤松義雅を攻め立て、八月二十八日真弓峠を突破し、坂本城に向って進軍した。
九月一日、坂本城は包囲された。三日になって満祐は坂本城を捨てて、木(きの)山(やま)城(兵庫県たつの市)で籠城し、最後の抵抗をするも山名一族の大軍に包囲され、十日に幕府軍の総攻撃が行われると覚悟を決めた満祐は教康や弟の則繁を城から脱出させたのち、安積行秀に介錯を命じ切腹して果てた。
その後、赤松一族は殺された者、自害して果てた者、逃亡した者と散り散りばらばらとなった。満祐の首は四条河原に晒された。
山名持豊は満祐を討ち果たした功績により、満祐の所有していた播磨を、山名教清は美作を、山名教之は備前を得て山名一族は三国の所領を手中に収め再び六分の一殿へと登り詰め、細川氏と覇を競うようになった。
足利幕府はこの一連の出来事で権威を失墜させただけでなく、折り悪くこの時代、異常気象による天候不順も災いして各地で「徳政」を要求して土(つち)一揆(いっき)が頻発し、都の治安が悪化していた。
これが結果的に二十六年後の応仁の乱へと繋がって時代を大きく動かしていくことになった。足利尊氏が「わが父」と呼んだ赤松則(のり)村(むら)(円心)が足利幕府を開くきっかけを作り、足利義教が「三尺入道」と呼んだ赤松満祐が足利幕府を閉じるさきがけともなった。足利幕府は赤松に始まり赤松にして終わったとも云える。
百島八幡神社のお弓神事は新しい年の吉凶を占うことや、豊作を祈る弓矢の霊力と神の御加護により、その年の悪霊を退散させるなどの信仰を意図したものであったことから、弓師(射手)に当たった頭屋(当屋)では、名誉と責任を感じ、家に七五三(しめ)縄( なわ)を張り、当主は水垢離(みずごり)を行って、修練稽古に励み、精(しょう)進(じん)を重ねたと言う。
頭屋(当屋)になることは厄除け(やくよけ)になり家の繁栄を約束されるとして、誇りをもって事に当たっていた。戦時中に頭屋制を輪番制に改め、現在では本村(ほんむら)(郷地区・坂地区を合併)で五名、福田で五名、泊で五名の合計十五名で奉祀している。
昭和四十七年には揃いの袴(はかま)・裃(かみしも)と弓矢が新調され、弓師(射手)の袴には赤松家所縁(ゆかり)の旗印である左三つ巴の紋(もん)が染め抜かれている。
当初この神事は、手作りの弓矢を使い、これを神殿に奉げ、神官の祝詞とお祓いの後、射場(いば)に出て四方に矢を放つことから幕を開けていた。
これは、棟上や地鎮祭などの時に行う「浄め(きよめ)」の奉(ほう)斎(さい)と同じで、毎年陰暦正月七日に行われていたが、戦後は一月十一日と改め、島の開運と家内繁栄厄除け祈願として継承されている。
的の直径は六十センチで二重丸を画いた中心に素焼きの「瓦(かわら)け」をつけ、十五メートルの距離から射手の十五人が太鼓の合図で一人二十本ほどの矢を的に向けて次々に競射する。
的中者には四十センチ前後の細い青竹の先に挟んだ白紙の祝儀袋が振舞われる。白紙の祝儀袋の表には金壱万両と書かれているが、中身に十円硬貨が一個納まっているのが御愛嬌である。
現在百島には「赤松」姓を名乗る島民も多く、西林寺から東に下りた本村(ほんむら)の荒神山の墓所には赤松一族の墓であると言われている「一石五輪塔」が残されている。墓所の柵の中には供養塔である「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」と、足利尊氏の覇業に貢献した赤松則村(円心)(法雲寺殿月潭円心大居士)の塚も建てられている。
さらに坂上(さこじょう)には赤松宗家の屋敷跡に「社(やしろ)」が祀られており、歴史の興味は尽きない。
PF・1
赤松満祐は赤松則村(円心)の曾孫にあたる。
PF・2
因島村上家には応永三十四年(1427)十二月十一日付けの足利四代将軍義持(よしもち)の御内書が残されている。
「播州でのこと(播磨国の赤松満祐討伐)について(村上備中入道(吉豊)は)早々に駆けつけてくれた 感心なことである。
今後も忠義を尽くしなさい」との書状である。(村上備中入道は因島村上家の系譜では最初に因島土生(はぶ)町の長崎城に入った人物とされる)これは応永三十四年十月に播磨の守護赤松満祐が将軍義持に反旗をひるがえし、京の宿舎に火をかけて播磨に下国したとき、村上備中入道(吉豊)が海上から赤松氏を攻めた事への感状である。
将軍義持は備後守護山名時(とき)煕(ひろ)(宗全の父)等に播磨国の赤松満祐の討伐を命じており、備後国の因島村上家も山名氏の指揮下で従軍していた事が分かる。正長元年(1428)十月二十日には時煕は村上備中入道に備後国沼隈郡多嶋(現福山市内海町)の地頭職を与えている。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット