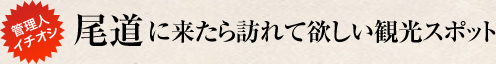![]()
京都の北野天満宮は学問・文芸の神様、天神様として修学旅行生を始め学業の向上等(など)を願う大勢の人達の参拝が絶えない。
御祭神は菅原道真、中将(ちゅうじょう)殿(どの)(菅原道真長男)、吉祥女(きっしょうじょ)(菅原道真夫人)である。非業の死を遂げた菅原道真(845~903)の怨霊を鎮めるために建てられた全国各地の一万二千社とも言われている天満宮・天神社の多くがこの北野天満宮より勧請(かんじょう)されている。
承和十二年(845)学者で中級貴族だった菅原是(これ)善(よし)の子として生まれた。京都下京区の菅大臣神社(菅原天満宮神社)は菅原道真が誕生した場所とされていて道真が産湯に使ったとされる井戸が残されている。

北野天満宮
菅原道真は幼い頃から詩歌に親しみ、十一歳で漢詩を詠んで周囲の人々を驚かせたと言われる。書は一度読んだだけで全て覚えてしまうという程で神童と称された。
十八歳で朝廷の試験に合格して大学寮という教育機関に学ぶ文章生(もんじょうしょう)となり、二十六歳で官僚登用試験に合格し役人となった。二十九歳で昇殿が許される五位となり、更に努力を重ね、元慶元年(877)三十三歳になった時には祖父清公、父是(これ)善(よし)と同じ大学寮の教官である文章(もんじょう)博士(はかせ)(中国の歴史と詩文の読解・漢詩文作成を学ぶ科目である文章道を大学で教授する教官)という地位について学者として名声を得た。
四十二歳の時には讃岐の国司となって地方の実態を学んだ。四年後の寛平二年(890)任期を終え、都に戻った道真は時の第五十九代宇多天皇に政治家としても能力を認められ、寛平三年(891)には宇多天皇の蔵人頭(天皇の主席秘書)に就任し重用されて朝廷内での地位を高めていった。
昌泰二年(899)に五十五歳で遂に右大臣に任命され、左大臣に任ぜられた藤原時平(ときひら)と共に天皇による政(まつりごと)を支えた。
当時太政大臣藤原基経(もとつね)(藤原北家)は絶対的な権力者であった。藤原氏は閨閥(けいばつ)によって我田引水的な政(まつりごと)を行い、権勢を我が物として後(のち)の摂関政治へと展開させ、藤原道長の世で頂点を迎えることになるのであるが、藤原氏が天皇以上の専権をふるうようになってから律令制の混乱が始まった。
仁和三年(887)宇多天皇も皇太子に引き上げてくれた基経の忠義に対して日本最初の関白に任じて報いでいた。その基経が寛平三年(891)亡くなってからは跡継ぎである藤原時平が二十代前半でまだ若いという事もあって宇多天皇は新たな関白を置かず自らの親政を行うようになった。
宇多天皇の母方が藤原氏の出身ではなかったこともあり、宇多天皇は政(まつりごと)に藤原氏以外にも広く人材を求めた。
道真もその一人であった。道真が宇多上皇の大和国巡幸に随行して東大寺の鎮守社である手(た)向山(むけやま)八幡宮に参拝した際に詠んだ「このたびは 幣(ぬさ)もとりあへず手(た)向山(むけやま) 紅葉(もみじ)の錦(にしき) 神のまにまに」(今回はここ手向山八幡宮への御参拝が突然でしたので神様に奉げる為の御進物の準備が出来ませんでしたが、美しく織りなされた錦のような境内の紅葉を御神前に奉げたいと思います)の和歌は藤原定家により小倉百人一首に加えられているが、日頃忙しい実務の諸事万端を手際よく取り仕切る堅実な実務官(詩臣)としての道真の姿が伺える。
混乱する唐の情勢を踏まえ、唐への派遣遣唐使を見直すよう進言したのも道真であった。
寛平九年(897)宇多天皇は退位され、七月に十三歳の敦(あつ)仁(きみ)親王が即位された。第六十代醍醐天皇である。
昌泰四年(901)、道真が右大臣になって二年後の五十七歳の時、藤原氏の既得権益を脅かす朝廷の財政再建策を打ち出したことから、左大臣の藤原時平はこれに反発し「いまだかって儒門(学者)から出た大臣はいない」と道真を尊大に見下しただけでなく、この際目障りな道真を罷免してしまおうと「道真は畏れ多くも醍醐天皇を廃して斎(とき)世(よ)親王(醍醐天皇の異母弟、道真の三女寧子(やすこ)の婿)を皇位に擁立しようと企てている。」との讒言(ざんげん)をふれまわった。
時平は宇多上皇が日頃、何かと道真を信頼し相談し頼りにしている事と、道真の博学多才を妬(ねた)んでおり、当時十七歳の醍醐天皇も宇多上皇からの寛平の御遺誠による天皇の心得を承知していたものの、予てより特に親しい二人の間柄には疑念を持っていたことから、「やはり道真は外戚政治を狙っていたのか」「道真に逆心あり、職務をわきまえず専横(せんおう)の野心を持ち、上皇(宇多上皇)を欺いただけでなく、天皇と皇弟(斎世親王)を反目させて間を裂くつもりか、もはや捨てては置けまい」と激怒され、昌泰四年(901)一月二十五日、道真を大宰(だざいの)員外(いんがい)帥(そち)に任ずるとの勅命(ちょくめい)を発せられた。
当時大宰府を実際に管理するのは次官大宰(だざいの)大(だい)弐(に)という事になっており、長官の大宰員外帥は一種の名誉職で赴任までする事は少なかったのであるが、道真の場合は実質的な流罪扱いであり、罪人として都を追われ衛兵に囲まれ遠く大宰府まで護送されることとなった。
突然無実の罪を着せられた道真は慌てて醍醐天皇に対して二心(ふたごころ)のないことをとりなしてもらおうと、退位された後(のち)仁和寺で出家されていた寛平法皇(宇多天皇)のもとに駆け付けた。
偶々法皇は御影堂にて勤行中であったため、水掛不動尊の前にあった石の上に腰掛けて勤行が終るまで待つことになった。(この時座っていた石を仁和寺では管公腰掛石と呼んでいる) 法皇が勤行を終わられた後、道真は「流れ行く われは水屑(みくず)となりはてぬ きみ柵(しがらみ)となりて とどめよ」(根も葉もない讒言によって私はまるで水草のように大宰府へ流される事になってしまいました。お願いですどうか水草を止める柵のように左遷の命を取り消して下さい)と一旦出された勅命が覆るのは難しい事を知っている道真は讒言(ざんげん)には何の根拠も無いことを法皇に懸命に訴えた。
日頃の道真の誠実さを承知している法皇は涙を流され、早速勅命を撤回させようと急いで内裏に馳せ参じた。しかし醍醐天皇は御所の大門を閉じ、父である法皇にも会おうとしなかった。それでも法皇は御門の前に茣(ご)蓙(ざ)を敷いて坐り、醍醐天皇が改悛(かいしゅん)してくれるのを一日中待ったが、何の応答も無く法皇は空(むな)しく仁和寺に帰らざるを得なかった。
結局、僅か一週間後の二月一日、道真は何も弁明も出来ぬまま都を去ることになった。道真は都を去る時、自宅の庭にあった梅に「東風(こち)吹かば におひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春なわすれそ」(この家に私が居なくなっても暖かい春になったら又、花を咲かせて香しい香りを放っておくれ)と、大宰府への配流が取り消される事はもう無いと諦めながらも、どうしてとの思いと、残していく家族への不安、気がかりを感じさせる和歌を詠んでいる。
大宰府への途中の国々には罪人である道真一行に食料も馬も供出してはならぬという時平のお触れが出されていて、行く先々で道長は自ら水や食料の交渉をして調達しなければならなかった。
このため二月二十五日、大宰府に到着した時にはすっかり体の調子を崩してしまっていた。しかも悪い事に大宰府に連れて来た幼い子供の隈(くま)麿(まろ)と紅姫の二人は病に倒れて亡くなり、道真は生きる気力も無くしてしまっていた。
道真は大宰府に赴任して二年後の延喜三年(903)二月二十五日、失意のうちに大宰府で亡くなった。五十九歳であった。
近年の調査で大宰府で道真の官舎としてあてがわれた都府楼の南館跡から発掘された土器は大宰府周辺から一般的に出土する高価な陶磁器でなく、素焼きの粗末な器ばかりであったことから、現地では道真は質素というより本当に貧しい暮らしを強いられていたのではないか、それも板葺きの簡素な屋敷で屋根は雨漏りし、床は抜け落ちたような家で暮らしていたのではないかと言われている。
大宰府市の文化財課の井上氏によると「道真は大宰府の長官としてやってきたが、左遷されて来たので朝廷の許しが貰えないため職務(仕事)は与えられず、生活水準も低く長官とは名ばかりであったのではないか」と語っておられる。
大宰府天満宮には道真が実際に書いたと言う「離家三四月 落涙百千行 萬事皆如夢 時々仰彼蒼」(都を離れて三ヶ月、四ヶ月が過ぎ、落とした涙は幾筋にも及ぶ、身の上に起こった事は全て夢のようだ、東の空を仰いで自らの定めを想うばかりである)との漢詩(掛軸)が残されている。道真には身に降りかかった現実を受け入れられず全ての事が夢の様であったのであろう。
こちらに来てまだ三四ヶ月であるのにもう都への帰還さえ断念せざるを得ない状況となっている。余程辛い生活を強いられていたのであろう。「大宰府に満ちる淡雪は白い梅の花に見える 日の光の中揺れる年の初めの梅の花 烏(からす)の頭の雪は懐かしい都の我が家に帰れる印かと思う」が道真の詠んだ最後の漢詩となった。
「烏(からす)の頭の雪」とは「烏(からす)の頭(かしら)が白くなる」との「史記」の故事に由来しており、春秋戦国時代「秦」の国の人質となっていた「燕(えん)」の国の皇太子「丹」に対して、「丹」を帰国させるつもりのない秦の王は「烏の頭が白くなり、馬に角が生える」という有り得ない事を帰国の条件としていた。が、後日実際に白い頭の烏と角の生えた馬が現れたとの事で「丹」は帰国が許されたと言う話がもとになっている。
後年南朝の後醍醐天皇の忠臣であった四条中納言隆資(たかすえ)はこの漢詩をもとに「カンコウ(還幸)と鳴くや吉野の山鳥頭も白し尾も白(面白)の夜(世)や」と北闕(ほっけつ)の天を望んだ天皇と共に都への帰還が叶うよう歌を詠んでいる。
自分は無実なのだから真実が明白になって京都に帰還(還幸(かんこう))する日が来るのではないかという淡い期待と、一方でそれは叶わぬ無理な願いであると考えざるを得ない現状に、自らに皮肉を込めて京都に残してきた家族の事や今の自分の厳しい暮らし向きを自嘲せざるを得ない道真の苦しい胸の内も痛いほど伝わって来る。
道真の亡くなった後、都では三年続きで疫病や天災等奇怪な出来事が続発した。道真左遷の片棒をかついだ参議の藤原菅根(すがね)が亡くなり、続いて道真の死から6年、延喜九年(909)に張本人の藤原時平が三十九歳の若さで熱病にかかって病死した。
時を同じくして長雨や干ばつ伝染病等変異が頻発するようになった。延長元年(923)には時平の娘婿である醍醐天皇の皇太子保(やす)明(あきら)親王も二十一歳で亡くなった。
その子の慶頼(よしより)親王もわずか五歳で病死した。恐れをなした醍醐天皇は今は亡き道真を右大臣に復し、正二位の位を追贈した。しかしこれで治まらず追い打ちをかけるように延長八年(930)宮中の清涼殿に落雷があり火災となって大納言の藤原清(きよ)貫(つら)等五人の死傷者が出た。(現在、国宝に指定されている「北野天神縁起絵巻」にこの様子が描き示されている。)醍醐天皇は落雷の直後から、御心痛を煩わし三ヶ月後、病に臥してまもなく崩御された。四十六歳であった。
もともと天神は雷神という天候を司る農耕神として信仰されていたが、この異変は道真の霊が雷神を都に遣わして祟っているものと信じ、雷神つまり天神は道真の怨霊と位置づけられ、道真が怨霊となり祟っているものと信じられた。
藤原氏や貴族達は恐れおののき、恐怖は頂点に達し、道真に太政大臣の位が贈られた上に、平安京の北野の地に道真の怨霊を鎮める為の社(天神社)が造営された。
北野天満宮の社殿の東側に「菅家(かんけ)遺誡(いかい)」からの出典による「和魂漢才(わこんかんさい)」との石碑が置かれている。
先の読めない激変する世界にあって、グローバルなスタンダードを取り込んで行く中で和を以て尊しとのアイデンティティを高めていきたい。
国家間の対立が激化によって国対国、地域対地域、人対人が分断され、孤立化が進んでいる今日、政治、経済、学術、人間関係等々あらゆる問題の行動規範に応用可能な道真の時代を超えた時宜(じぎ)を得た含蓄のあるメッセージであるような気がする。
PF
菅原道真は明治二十一年(1888)発行の五円札として、明治十四年(1881)発行の神(じん)功(ぐう)皇后の一円札に次いで二番目の肖像入りの紙幣として発券された。明治の廃藩置県の少し前には姫路城が二十三円で売りに出されていた。
御袖八幡宮の伝説
延喜元年(901)六月二十四日、九州大宰府に赴(おもむ)く途中、道真は尾道長江の浦に船を停めている。たまたま近くで農作業中の金屋某なる者が道真を親切にもてなし、小麦餅と甘酒を振舞った。
このことに感謝した道真は衣の片袖に自画像を描いて家主に与えたと言う。この袖を御神体として御袖(みそで)御影(みかげ)天神(てんじん)と尊称した(金屋大神とも言う)御袖天満宮が尾道市長江一町目に鎮座している。
石段を左側に入った所に菅公が腰を掛けられたと言われる石が現存しており、金屋某が農耕中であった畑と言われる場所では、現在でも天神社にお供え用の小麦が作られている。

御袖八幡宮石段と随身門
この御袖八幡宮の正面参道を進み、広島藩主浅野夫人が寄進した左大臣の阿形(あぎょう)像と右大臣の吽形(うんぎょう)像の随身門から本殿に至る五十五段の石段は明治三十六年(1903)に巾五百十五センチ、踏面三十一センチ、蹴上十七センチのサイズに花崗岩から一本物に打ち出して敷設(ふせつ)され造営されている。
その石段の最上段の五十五段目だけが意識的に一本ものでなく継がれて敷設されており、満ちれば欠けるの格言を実践している。「我が技術、未だ未熟なり」という尾道石工(いしく)の謙虚な心意気を示しているとも言われている。
決して得意になるなと言う戒(いまし)めの細工とも言われている。又、江戸中期に築造されたという石段の両側の石垣も、上に行くほど巨石が積み上げられており、レッカーやクレーンの無い時代、尾道石工の心意気を感じる造作(ぞうさく)である。
さらに境内には文化六年(1839)と彫られた台座の上に「さすり牛」と名付けられた尾道石工による臥(が)牛(ぎゅう)の石像がある。固い御影石を彫り込んで台座石より頭を左の本殿に向けて出し、微笑んでいるようなその顔の表情もこれまた見事と言うしかない。
冠天神社の伝説
延喜元年(901)六月二十三日、道真は大宰府に下向の時、古江(こえ)の浦(尾道市向東町古江浜)に船を寄せられた。
道真は長い船旅で疲れていた。暑かったこともあって、船を降りるとすぐ北東の丘に登り、頭に被っていた冠を解いて大岩の上に腰をかけ瀬戸内海の美しい景色を眺めてくつろいでいた。そこにたまたま居合わせた土地の農夫が道真に麦餅と甘酒を振舞ったと言う。
その後、この丘は天神山と名づけられ、冠天神社が創建された。道真が冠を解いて置いたと言う大岩が磐座(いわくら)で御神体となっており、この大岩を冠岩と称している。
この冠岩に登ると直ちに神罰を受けると言い伝えられており、江戸時代にこの岩に登ろうとした人が発狂したとの話が残っている。又、冠岩を雨露にさらすのはしのびないので神殿を建てようとしたところ、天神山がにわかに鳴り動いたということがあったので、現在でも御神体の冠岩はそのまま屋外にある。
この伝説のせいかどうか、古江浜には「天神(てんじ)」という地域もあり、この付近には「冠」「冠野」など「冠」を使った苗字のお宅が散見される。
宇立天神社の伝説
延喜元年(901)、道真が西下の時、当時入り江のある良港であった宇(う)立(だつ)(尾道市向島町宇(う)立(だつ))に船を停め休息をとった。
土地の人が小麦をたいて甘酒と供に差し上げると道真はたいそう喜んで手に持っていた笏(しゃく)(官位にある者が礼装したときに帯の間にはさみ持ち、備忘のために君命などを書き留めた薄い板)を与えたと言う。このことから宇立天神を笏天神と尊称している。尾道大橋を渡り、歌島橋東詰を左に曲がり住宅街を抜けた所にこの天神社は建っている。
尾道では菅原道真についての伝説はこの三ヶ所のほか百島と御調などでも語り継がれている。
又、瀬戸田町では道真が讃岐守の時代の話が伝承されている。非業の死を遂げた道真公に対する慰霊と鎮魂の思いが様々な形で語り伝えられている。
これは尾道ではこうした情報がいち早く受け入れられることの出来た文化的成熟度の比較的高い地域であったことと、無念の思いの弱者を悼む仁愛の精神を持ち合わせていた土地柄、風土であったことも示しているのではないか。
又、道真公が残していったものが御袖、冠、笏の違いはあるが、西下する道真公をもてなした物が不思議なことに小麦餅と甘酒であったことが共通しているのも面白い。
もともと原本があって小麦餅と甘酒の部分は変わらずに語り伝えられてきて、御袖と冠と笏の部分だけが変化してきたとも考えられる。そんなに離れていない尾道の三つの場所で造営された道真公を祀る神社が何を願って建てられたのか、語り継がれてきた伝説は何を伝えたかったのであろうか。
もちろん道真公の聡明さにあやかりたい、学問向上成就の願いもあるであろう。しかしそれ以上に、道真公の亡くなった後に都で起った天変地異を教訓として戒め「人を呪わば穴二つ」(人を恨んではいけない。皆と仲良くしなさい)「天知る、地知る、我が知る」(人として正しい行いをしなさい)との京都人の処世訓が語り継がれこの土地への災いを回避しようとして伝播して定着したのではないだろうか。
道真の詠んだ「心だに 誠の道に かなひなば いのらずとても 神やまもらむ」(誠の心をもって日々最善を尽くして生きなさい)との道真公の思いが浸透しているのであろう。
尾道には「ふなやき」という数百年の歴史を持つ御菓子がある。これは小麦粉を水で捏ねて焼鍋の上で薄く伸ばして焼き、味噌を塗って食べたのが始まりで、砂糖の入手が容易になるにつれて、現在の「ふなやき」になったのであるという。
道真公をもてなしたのが、このふなやき(小麦餅)であったという話もある。尾道ではこの「ふなやき」を旧暦の六月一日に食べると夏病みしないと言われている。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット