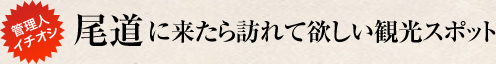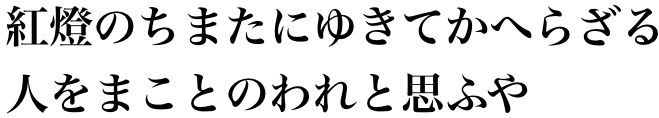
「かにかくに祇園はこひし寐るときも枕の下を水のながるる」
淡い哀感の漂うこの歌は吉井勇が明治四十三年(1910)九月に発表した「酒ほがひ」に収められている。この歌集の口絵は木下杢太郎が描き、装幀は高村光太郎である。
当時二十五歳の勇はその頃出ていた文芸雑誌「趣味」の五月号に書いた戯曲「偶像」によって始めて得た原稿料十円で京都に遊び、この歌を六月の「スバル」及び「祇園冊子」に発表している。当時の勇の歌は紅燈の巷で酒や女性に心を奪われながら作られた歌とも言えなくもないのであるが、私達にどこか懐かしい哀歓を感じさせ心に沁み込んで行く。
本人も「これ等の歌は芸術的価値もそう低くないというだけの自信がある」と語っている。吉井を最も歌人らしい歌人として熱心な讃美者の一人で、無二の親友でもあった谷崎潤一郎はこの歌の元歌は確か「かにかくに祇園は嬉し酔ひざめの枕の下を水の流るる」であったように思うのであるが、作者は考えるところがあって後年今のような形に訂正したのではないか、私は老後の作者が若い時に用いた奔放な言葉を穏やかな字句に改める気持ちも分からなくはないが、私にはもとの形の方が感じがぴったり来ると随筆「磯田多佳女のこと」で述べている。
吉井がこの歌の着想を得たのは祇園の茶屋「大友(だいとも)」であった。四条通と縄手通が交差する角を北に上がり、二~三百メートルほどいった先に白川に架かる明治四十五年完成の石造りの大和橋がある。
現在この大和橋を渡った東西の新橋通は路面電車の敷石を使った石畳の車道と歩道とになっているが、当時はこの車道部分に茶屋が軒を並べていた。

かにかくに歌碑
つまり、白川を挟んで南と北の両岸に茶屋が建ち並んでいた。「大友」は大和橋を渡り現在の新橋通の歩道の角から数えて二、三筋目の露地を右に入ったところにあった。
町名は東山区新橋縄手通東入ル元吉町である。この「大友」の女将磯田多佳の居間であった一階奥の三畳の間は白川の水面に突き出すような形で造られており、伽羅(きゃら)の臭いが染み込んでいたという部屋では床下を流れるせせらぎの音が聞こえていた。
第二次世界大戦下の昭和二十年三月、空爆の疎開対策で現在この歌碑が建っているこの地にあった茶屋「大友」も疎開させられることになった。
当時多佳は病床にあって三月十七日、姪の息子に手を引かれてこの家を後にした。そして南禅寺の北之坊に移ると直ぐに病んで立てないようになり、二か月後の五月十五日六十六歳で亡くなった。
白川の北側の家々は強制撤去されて防火帯となり、「大友」があった場所も野菜畑になったのを多佳が目にすることがなかったのはせめてもの慰めであったであろう。
多佳は三味線や俳句や絵画を良くし、類(たぐい)まれな教養から文芸芸妓と呼ばれていた。二十六から二十七歳の頃、芸の道を退いてからは母ともがやっていた実家の「大友」の女将として才女ぶりを発揮し、趣味を同じくする文人・墨客が大勢「大友」に集まった。
夏目漱石もその一人で大正四年に本人と多佳を詠った俳句で「春の川を隔て男女(おとこおんな)哉」と子規の手ほどきを受けた洒落た腕前を披露している。多佳をいたく気に入っていた漱石は、ある時多佳を嵯峨野の桜見物(北野天満宮の梅とも)に誘った。
「おおきに、よおおすなぁ」との多佳の返事に漱石は約束がなったものとばかり思って、思い込んでいた場所で待っていたが、結局待ちぼうけを食わされたとのエピソードも残っている。
谷崎潤一郎は多佳の訃報に接し「しら河の流れのうへに枕せし人もすみかもあとなかりけり」「あぢさゐの花に心を残しけん人のゆくへもしら川の水」と詠んでいる。多佳は紫陽花の花が好きであった
昭和三十年十一月八日、京都の名声を高めた功績にと友人たちにより吉井勇の古希(七十歳)の祝いとして「大友」の跡地にこの歌碑が建立された。当時のお金五十万円ほどであったという。
この歌碑は堂本印象の着想で「東山」という頼山陽の端唄「蒲団着て寝たる姿は古めかし、起きて春めく知恩院云々」から石の姿を東山になぞらえた縦九十センチ、横百八十センチほどの大きさの鞍馬石に歌を刻んでいる。歌碑の敷地の片隅に多佳が好きであった紫陽花(あじさい)の花が植えてあるのも一興である。ちなみにこの「東山」という端唄を多佳は好んでよく三味線で弾き語りをしていたという。
この除幕式で勇は「僕の嬉しい日だ。生きているうちからお祭りをしてくれるのだから実に楽しいよ」と感激していたという。勇はこの建碑記念の御礼にお世話になった方々に清水焼の夫婦茶碗を焼いて送っている。
この除幕式には四世井上八千代(京舞井上流家元)、大谷竹次郎(実業家)、大仏(おさらぎ)次郎(小説家)、久保田万太郎(俳人・劇作家)、里見敦(小説家)、志賀直哉(小説家)、新村(しんむら)出(いずる)(言語学者)、杉浦治郎左衛門(祇園一力当主)、高橋誠一郎(芸術院院長)、高山義三(よしぞう)(第十八代京都市長)、谷崎潤一郎(小説家)、堂本印象(画家)、中島勝蔵(祇園甲部取締役)、西山翠嶂(日本画家)、湯川秀樹(物理学者)、和田三造(洋画家・版画家)の錚錚(そうそう)たるメンバーが発起人となっている。
一時期もう世に出る事はないだろうと考えていた勇であったが、昭和二十三年一月宮中の歌会始めの選者に任ぜられ、十月には遅蒔きながら日本芸術院会員にも選ばれている。昭和二十五年には始めて都をどりの歌詞「京洛名所鑑」を作り、南座で上演された。
以来都をどりの台本作りは勇が亡くなるまで続いた。今年も四月一日から「みやこをどりはヨーイヤサー」のかけ声とともに京都に春を呼び込んでいる。
起伏の多かった人生は歌だけでなく勇の人間味と重厚感を増していったが病魔には勝てず、昭和三十五年(1960)十一月十九日、胃癌が転移した肺癌により七十五歳の人生の幕を閉じた。亡くなった時の言葉は「歌を」「歌を」であったという。約束していた小学校の五十周年を記念する校歌作詞の事も気になっていたのかもしれない。
毎年十一月八日には祇園甲部の年行事として芸舞妓が歌碑に白菊を手向けて吉井勇を偲ぶ「かにかくに祭」が行われている。
当日は歌碑の周りにマスコミ関係者や多くのファンが訪れている。歌碑を中心としたこうした華やかな祭事が毎年開かれているのは全国的にも珍しい。この「かにかくに祭」も京都の多くの人々の関わりの中で京都の秋の風物詩となっている。
京都と京都人の懐の広さと文化の豊かさが感じられ頭が下がる思いである。勇は今も悠々として静かにニコニコと笑ってこれを見守っていることであろう。
勇は「歌碑については「人生の記念碑」である」と言っているが、大正五年(1913)六月に発表した「昨日まで」の歌集の中に「紅燈」と題して
「紅燈のちまたにゆきてかへらざる人をまことのわれと思ふや」
と、紅燈の巷での頽(たい)唐(とう)的な惑溺(わくでき)した自分を「昨日まで」として、新しい人生を目指そうとする歌を詠っているが、それでも勇はこの「かにかくにの碑」については最も親しみを感じる歌碑であると述べている。「かにかくに」の歌について「ただ一つ私の旅の愁いを慰めてくれるものに、あの加茂川(白川)のせせらぎの音があったことを私はどうしても忘れることが出来ない」と「草珊瑚」で語っている。祇園に建ったこの歌碑こそ間違いなく勇の一時代を画する「人生の記念碑」というのに相応しい一つと言って良いであろう。
比叡山からの湧水と琵琶湖疏水が合流した白川であるが、新橋通り付近の白川は川幅が七、八メートル、深さ十五センチ程のささやかな流れで、白川砂雑(ま)じりの川底の上をさらさらと小さな波を送り出しながら、新橋を南に下ってきた川の水は木造りの巽橋の所で西に流れを変えて、枝垂桜の枝を掠(かす)め「かにかくにの碑」の南側を通って大和橋に向かい鴨川にそそいでいる。
この白川に架かる石造りの大和橋に嵌(は)め込んである「花洛名勝図会」の「大和橋」の画(え)(幕末の元治元年(1864刊行)には当時の縄手通の大和橋の上を行き交う人々や白川北側の立ち退いた茶屋の一部と柳の大木が描かれており、これを見ると白川の川幅は今より広かったように感じられる。石ばしのはだもぬるむか春の水」というはんなりした歌も添えられている。

伏見の戦跡石碑
「伽羅の香がむせぶばかりににほひ来る祇園の街のゆきずりもよし」
「先斗町の遊びの家の灯のうつる水なつかしや君とながむる」
末吉町の茶屋から出て川端通りの河岸から鴨川を挟んだ向う岸の先斗町の燈を見て、気持ちを高揚させながら歩いている若き日の勇の姿が彷彿(ほうふつ)とされる。
京都の吉井勇に関する記念碑の一つといっても良いであろう石碑が、京都伏見区の御(ご)香宮(こうのみや)神社境内にもある。「伏見の戦跡」という元内閣総理大臣の佐藤栄作氏の揮毫による石碑である。
この石碑の由緒書に「慶応三年十二月九日、王政復古が渙発(かんぱつ)せられるや京洛の内外は物情騒然として朝幕の間に一触即発の険悪な空気が漲(みなぎ)った。ところが七日の明方御香宮神社の表門に「徳川陣営」と書いた大きな木札が掲げられた。
祠官(しかん)三木善(よし)郷(さと)は早速社人を遣わして御所に注進すると、翌日薩摩藩の吉井孝助(後の宮内大臣吉井友(とも)実(ざね)・吉井勇の祖父)が来て、この札を外してここに部隊を置いた。云々」と書かれている。
慶応四年一月三日鳥羽街道の小枝橋で鳴響いた砲声によって戦端が開かれ、御香宮と目と鼻の先にある伏見奉行所(現在桃陵団地)の旧幕府軍との間で砲撃が開始された。
正にここが江戸から明治へとその後の日本の方向を決定した「鳥羽伏見の戦い」の伏見の舞台の端緒の地となった。一月五日、鳥羽街道上の新政府軍の陣地に赤い布地に金銀で日月の模様を刺繍した錦旗(きんき)(錦の御旗)が翻るや、賊軍となった旧幕府軍は戦意を失い各地で敗退していった。
「思ひきや彌彦(やひこ)の山を右手に見て立ちかへる日のありぬべしとは」の歌は「「三峯」と号した勇の祖父友(とも)実(ざね)が、明治維新の際、西園寺公望(きんもち)を征討総督として越後方面で戦った軍旅の中で参謀として加わっていたが、河合継之助のいた長岡の戦いを始めその他各地とも苦しい戦いの連続であった。
この歌は命はないものと覚悟して望んだ戦いに勝って帰る凱旋の途(みち)すがら遥かに彌彦山(やひこさん)を遠望して詠んだ歌である。勇の父幸蔵は「この歌を薩摩琵琶でも吟ずるような調子で勇にうたって聴かせてくれた」(歌がたり・私の歌の半生より)という。
このことが勇にとって「歌に対する愛着の念を持つようになったとすれば、祖父は私にとって、或る意味での歌の師と云ってもいいであろう。」と語っている。祖父友(とも)実(ざね)は明治二十四年(1891)勇が六歳の時、享年六十四歳で亡くなっているので、勇にはそれほど深い記憶は残っていないはずなのに、昭和十七年勇が京大病院で生死をさまよう大病を患った時、最も多く勇の心にのぼったものはおぼろげな祖父の面影であったという。
勇には祖父が激動する時代に命を賭して持ち続けてきた高邁な精神と祖父自身の文人的なDNAが自分の中で重なり合っているのを感じていた。このことは勇にとって祖父の御維新での功績により吉井家が伯爵という華族に列せられていたことよりもはるかに重要なことであった。それほど祖父は歌人吉井勇にとって大きな存在であった。
「おほちちの戊辰のころの胸痛み心いたみを思ひつつぞ病む」
付記
「かにかくにの碑」にほど近い東山区の縄手通三条を下ったところにお茶漬鰻で評判の老舗「かね正」がある。
この店の鰻を適当な大きさに切って、熱いご飯の間に挟み、塩、山葵、山椒等(など)のお好みの薬味をのせて、熱い煎茶等をかけて頂くと柔らかで独特の風雅な味がたまらなく美味い。
実はこの店の先々代の大将が吉井勇と懇意であったことから、大将が吉井勇に頼んで作ってもらった歌が今もこの店の包装紙に使われている。
「かね正の茶漬うなぎの味に似て情の深さわれに得しめよ」
鰻の味に託けて昨今段々と薄れていくが人生の要諦は仁愛にあると勇は伝えたかったのかも知れない。
ゴンドラの唄
「ゴンドラの唄」は大正四年(1915)、島村抱月(1871~1918)の主宰する芸術座がロシアの作家ツルゲーネフの長編小説「其(その)前夜」を舞台化し、帝国劇場においてエレーナ役の松井須磨子(1886~1919)の主演で上演され、その四幕の「ヴェネツィアの町 大運河の岸」にての場面で歌われた劇中歌であった。
この舞台の脚本家であった芸術座の楠山(くすやま)正雄(1884~1950)が親交のあった吉井勇にこの劇中歌の作詞を依頼し、出来上がったのがこの「ゴンドラの唄」である。「其前夜」の大意は、幸福な家庭生活が担保されていた結婚を敢(あえ)て選択せず、主人公のエレーナが選んだのはロシアに亡命中の貧しいブルガリア人であるインサーロフであった。
二人で動乱化のブルガリアに向う途中、ヴェネツィアの町をゴンドラで探索するのであるが、インサーロフはヴェネツィアで病死してしまうという物語である。
前年に芸術座はトルストイの小説をもとに抱月が脚色した「復活」の舞台が好評で、各地で興行が行われていた。
この舞台でカチューシャ役の須磨子の歌う劇中歌の「カチューシャの唄」はレコードにも吹き込まれ、二万枚以上の大ヒット曲となっていた。
吉井勇は随筆「いのち短し」でこの「ゴンドラの唄」は森鴎外先生が訳されたアンデルセン原作の「即興詩人」の中の「妄想」という章の中の一節を典拠としたものであると述べている。
この著作は森鴎外が森林太郎の名前で明治三十五年(1902)九月一日、アンデルセン原作の翻訳本「即興詩人」上・下を春陽堂から発行したものであった。
その下巻の中の「妄想」との章に、主人公の即興詩人アントニオが北イタリアのエネチア(ヴェネツィア)に向う同じ船に乗り合わせていた少年達がエネチアの俚謡(りよう)(民間のはやり歌)を歌うというくだりがあって「其歌は人生の短きと戀愛の幸あるとを言へり。こ々に大概を意譯せんか。其辭にいはく。
朱の唇に觸れよ、誰か汝の明日猶在るを知らん。戀せよ、汝の心の猶少く、汝の血の猶熱き間に。
白髪は死の花にして、その咲(注)くや心の火は消え、血は氷とならんとす。来れ、彼輕舸の中に。二人はその盖(おほい)の下に隠れて、窓を塞ぎ戸を閉ぢ、人の来り覗ふことを許さ々(、、)らん。少女よ、人は二人の戀の恋の幸を覗はざるべし。二人は波の上に漂ひ、波は相推し相就き、二人も亦相推し相就くこと其波の如くならん。
變せよ、汝の心の猶少く、汝の血の猶熱き間に。汝の幸を知るものは、唯々(、、)不言の夜あるのみ、唯々(、、)起伏の波あるのみ。
老は至らんとす、氷と雪ともて汝の血を殺さん為に」との訳文と、次の章の「水の都」で主人公が初めて「ゴンドラ」という小舟を見て、「皆黒塗にして、その形狭く長く、波を截りて走ること弦を離れし箭に似たり。逼りて視(注)れば、中央なる船房にも黒き布を覆へり。
水の上なる柩とやいふべき」(注は原文に非ず)などとの訳文があって、勇はこれ等からヒントを得て作詞をしたという事になる。
翻訳本が刊行された明治三十五年九月と言えば勇が十六歳になる一ヶ月前のことであり、勇は青年期にこの本を読んでいて、強い印象を受けていたのであろう。この歌はアントニオの恋人であったアヌンチャタの物語の後半の展開を暗示させるものとなっているが、奇しくも当時勇が密かに慕っていた舞台女優松井須磨子のその後の運命にも影を落としていく事になった。
大正四年(1915)四月一日に発表されたこの「ゴンドラの唄」は前年「カチューシャの唄」を手掛けた中山晋平により作曲された。
「ゴンドラの唄」と「カチューシャの唄」はともに大正ロマンを彷彿させる歌であるが、その当時「ゴンドラの唄」は「カチューシャの唄」ほど当たらなかった。
しかし、この「ゴンドラの唄」が再び注目されたのは昭和二十七年(1952)の芸術祭参加作品で黒澤明監督による映画「生きる」の主題歌に採用されたことが切欠(きっかけ)であった。志村喬(1905~1982)が演じる市役所の市民課に勤める渡辺課長は、それまでは渾(あだ)名(な)をミイラと渾名されるほど死んだも同然な無気力な日々を過ごしていた。
ところがある日病院で自分が胃癌に罹っており余命が僅かなことを知って愕然(がくぜん)とする。自暴自棄になった彼は飲めない酒に心の苦悶(くもん)を紛らわして、キャバレーで思わず涙を流しながらこの「ゴンドラの唄」を歌う。
そしてこれを契機に何かに憑(とりつ)かれたようにがむしゃらに仕事に打ち込んでいく。その甲斐あって漸(ようや)く出来上がった児童公園で雪の降る中、ブランコに乗って今度はどこか楽しそうにしみじみと、この「ゴンドラの唄」を歌うシーンには胸を打たれる。
この映画は黒澤明監督の代表作であり、志村喬の渾身の演技が胸を打つヒューマンドラマの名作である。
ニューヨークタイムズ紙は志村喬を「世界一の名優」と絶賛している。
製作年度からどうしてもセピア色の感のある映画となってしまうことは致し方ないが、人や社会との繋がりが希薄になっている今日、「今をどう生きるか」ということを考えさせられる古くて新しい映画である。
ゴンドラの唄 (作詞・吉井勇 作曲・中山晋平) 「セノオ楽譜」大正五年六月
一、いのち短(みじか)し、戀(こひ)せよ、少女(おとめ)、
朱(あか)き唇(くちびる)、褪(あ)せぬ間(ま)に
熱(あつ)き血液(ちしお)の冷(ひ)えぬ間(ま)に
明日(あす)の月日(つきひ)はないものを。
二、いのち短(みじか)し、戀(こひ)せよ、少女(おとめ)、
いざ手(て)を取(と)りて彼(か)の舟(ふね)に、
いざ燃(も)ゆる頬(ほ)を君(きみ)が頬(ほ)に
ここは誰(た)れも来(こ)ぬものを。
三、いのち短(みじか)し、戀(こひ)せよ、少女(おとめ)、
波(なみ)にただよひ波(なみ)の様(よ)に、
君(きみ)が柔手(やはて)を我(わ)が肩(かた)に
ここには人目(ひとめ)ないものを。
四、いのち短(みじか)し、戀(こひ)せよ、少女(おとめ)、
黒髪(くろかみ)の色(いろ)、褪(あ)せぬ間(ま)に
心(こころ)のほのほ消(き)えぬ間(ま)に
今日(けふ)はふたたび来(こ)ぬものを

吉井勇旧居跡地((京都市左京区石橋町19)
PF
この「ゴンドラの唄」は今まで劇の上演以前の「底本」は存在しないと考えられていたが、この「ゴンドラの唄」が初めて掲載されたのが、当時の首相大隈重信が主宰する総合雑誌「新日本」第5巻第四号(大正四年(1915)四月発行)であることを、令和三年(2021)に吉井勇研究の第一人者細川光洋教授(静岡県立大学)が発見された。
その文藝付録には「この歌は近くに芸術座に於て上演さるべき「其前夜」劇に於て松井須磨子氏のうたふべき歌なり」と断りが書かれている。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット