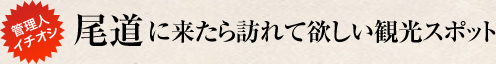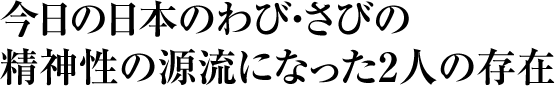
足利八代将軍義(よし)政(まさ)は永享八年(1436)、六代将軍義教(よしのり)を父とし、藤原鎌足の流れを汲むとされる藤原(ふじわら)北家(ほっけ)の公家日野重光の娘重子を母として、兄義勝の二つ違いの弟として生まれた。
しかし、父義教が播磨の守護大名赤松満祐によって暗殺されたことで後を継いだ兄義勝が七代将軍になったのであるが、十歳で赤痢で早世したことにより義政の人生が一変した。総領でなかったことから本来なら仏門に入り僧侶として一生を送るはずであったが、義勝と同じ母重子の子である義政がわずか八歳で足利家の家督を継いだ。政務は幼い義政に代わって管領の畠山持国が担当した。
十四歳で元服した義政は正式に八代将軍の座(ざ)に就いた。しかし当時の室町幕府は財政基盤が脆弱な上に、守護大名の合議制による幕府の政策決定機構が上手く機能していなかった。その上、荘園領主達は課税のしわよせを農民に押し付けたため、各地で土一揆が起っており政権は不安定そのものであった。
康正元年(1455)八月、義政が十九歳の時、日野家から将軍家に嫁ぐべく英才教育を受けて育った十六歳の富子を正妻に迎えた。母日野重子にとって自分の兄の孫である富子が花嫁として来てくれたことは喜ばしい事であった。
四年後、富子は夫婦が待ち望んだ望んだ待望の男子を出産したが、生後間もなく亡くなった。富子はこの事を義政の乳母(めのと)(側室)の御今(いまお)が調伏(ちょうぶく)(呪い殺した)したとの噂を信じて、御今を琵琶湖に浮かぶ沖ノ島に島流しにした。
それで事は収まった様にも見えたが、それでもなお富子は沖ノ島が京に近いからという理由で納得出来ず、御今を自刃に追い込んだ。
この事件は御今が幕府の奉公衆を務めた大館氏の出身で政治にも通じていた事もあって、幕政にも口を出していた事を快く思っていなかった母日野重子の計略によるものという説もある。
長禄三年(1459)は長期の干ばつや長雨が襲い農作物は大きな被害を蒙り大飢饉となった。税収源である農作物の収穫が減った事で、元々傾いていた幕府の財政は逼迫していった。
義政も始めのうちはなんとかして叔父の義満や父義教のように将軍親政を目指そうと努力していたが、将軍としてこれといった成果を上げられなかった。これは政治家として義政の資質の欠如によるところが大であるが、何と言っても武家の棟梁としては性格が優しすぎた。細川氏、山名氏、畠山氏、斯波氏等の守護大名を服従させることが出来ず、彼等の領土争いや跡目争いで天下が混乱していく中で、幕府の権威は徐々に凋落していった。
義政自身は政治への情熱を失っていった。第一子が亡くなってから中々子を授からなかった義政は自らに代わる後継者として天台宗の門跡寺院である浄土寺で仏門に入っていた三歳年下の弟の義(よし)視(み)に白羽の矢を立てた。義視は固辞していたが、義政から「仮に男子が産まれてもその児は仏門に入れさせる」と説得され無理矢理還俗させられた。
義政は義視を猶子となして後継者とし、細川勝元を執事として自身は政界から身を引こうとした。ところがその次の年の寛正六年(1465)十一月、富子が男子(義(よし)尚(ひさ))を出産した。義視を次の将軍にするとしていた義政と、我が子を将軍にさせようとする妻富子とは決定的に対立することとなった。
富子は義政を疎んじて、母重子の兄の大納言日野勝光と結託し、次期将軍義尚の代理であると言わんばかりに幕政にも口を挟み、次第に義政に代わって富子の幕府内での発言権は増していった。
後に応仁の乱と呼ばれる争いは義視の後見人となった幕府髄一の実力者の細川勝元と、勝元に次ぐ実力者であった山名持豊(宗全)との勢力争いから始まった。義政はただ時の流れに為すがままで将軍として口を挟む事が出来なかった。
初めは細川方が有利に進んでいたが、山名一族は領国から京に兵が続々入って来て攻め上がり、相国寺での合戦で勝利を収めると、一旦戦いは膠着状態に入った。
開戦二年目には義視があろうことか山名宗全の屋敷に駆け込んだ事で、山名方では西の幕府との口実となった。それに対し富子・義尚は細川方についた。この事が戦いを更に紛糾させ、長引かせた。更に畠山氏や斯波氏の管領家の家督争いも絡んで応仁の乱は細川の東軍、山名の西軍に別れてその後十一年にわたって戦乱が続いていくことになった。
戦いは一進一退を繰り返しながら泥沼化していった。文明五年(1473)、細川勝元と山名宗全が相次いで亡くなると、やっと応仁の乱の鎮静化が図られていった。元々政治への関心を失っていた義政は将軍職をこの年九歳となり元服を迎えた息子の義(よし)尚(ひさ)に譲った。未練など微塵も無かった。
義尚は晴れて第九代将軍となった。富子は義尚の後ろ盾となって事実上政治の舵取りをすることとなった。文明十三年(1481)春、義政は富子との軋轢から、妻との関係を完全に断って文明十四年二月四日、予てより計画していた東山山荘の造営を始めた。
政治への興味は失ったが東山山荘の造営に対しては寝食を忘れて情熱を注いだ。文明十五年六月二十七日、常(つね)御所(ごしょ)が完成すると直ちに室町御所を出て富子と別居した。
義政が新居に移り住んだ翌日、後土御門天皇から「東山殿」との称号を賜った。禅室(西指(せいし)庵(あん))、東求堂(とうぐどう)、会所(かいしょ)(はれの建物)、泉殿(香座敷)と次々に竣工していく中で、突然、義政は文明十七年(1485)六月十五日、嵯峨野の臨済宗の臨川寺で出家した。臨済禅の僧として得度し、法号を祖父の源道義に倣い道慶と名乗った。
剃髪を取り仕切ったのは相国寺の横川景(おうせんけい)三(さん)であった。横川禅師は当時五山文学の第一人者であった。禅師から学んだ禅宗として禅の正統な道徳律である「清貧」な考え方は義政の求めていた静謐な感覚を更に研ぎ澄ましていった。
只、義政は禅宗だけでなく持仏堂の名称を「東求堂」(東方の人、西方の浄土を求める)と名を付けたり、東求堂の正面には極楽浄土をイメージした蓮池を造ったりして、浄土信仰にもこだわりを持っていた。
東求堂は四畳半茶室の起源とされ、現代の和室の原型と言われているが、畳敷きの四畳に半畳を加えた微妙な広さに義政は何を求めたのであろうか。
義政は東山山荘の中心となる観音殿(銀閣)を造るのに当たっては祖父義満の残した舎利殿(金閣)に倣(なら)おうと舎利殿(金閣)に下見に出かけている。
そもそも、この東山殿の造営については横川禅師を相談相手として、全体像は西芳寺(苔寺)を手本として造られており、建物の名称や庭園の造形などの他は全て西芳寺に倣っていた。義政は造営にあたって、特別税をかけ資金を調達し、資材や巨岩、巨石、植栽などを有力守護大名、有力寺院などから強引に献上させた。
しかし慢性の資金不足や賛同者の少なさからしばしば工事を遅延せざるを得なかった。幕府の政策を立案する立場にいた富子には足利家の所有の荘園や守護大名等からの献金や献上品が集まっていた。京へ入る街道口には内裏修理との名目で通行税を徴収したのも富子の考案であった。富子には今のお金で七十億円もの貯蓄があったと言われている。
それでも富子は義政に資金援助をしようとはしなかった。しかしこの事が工事に賭ける義政の情熱を損なうものではなかった。富子は息子義尚の政治が上手く回る様、戦争終結の為の費用や痛んだ内裏の修繕、寺社の復興、公家への援助等使うべきところにはお金を惜しまなかった。
長享三年(1489)に観音殿(銀閣)の立柱式が行われたが、延徳二年(1490)、義政は観音殿(銀閣)の完成を見ること無く脳卒中により延徳二年(1490)一月七日、五十六歳で亡くなった。
観音殿(銀閣)の内外を黒漆で塗りおえた状態で亡くなったので、金箔張りの金閣に倣(なら)って黒漆の上に銀箔を張るつもりでいたかどうかは今となっては分からないが、近年の改修の際に一部に極彩色に彩られていたと思われる跡が発見されている。
観音殿のこの建物は二層からなり、一層の心空殿は書院風で、二層の潮音閣は板壁に花頭窓を設えた唐様となっており、室内には観音殿の名前の由来になった古木の中にすっぽりと納まった洞中観音と呼ばれる観音菩薩が祀られている。借景の東山を取り込んだ自然と一体になった庭園の風情も見事である。
現在、慈照寺(銀閣寺)の裏山を登った展望所となっている高台からは遥かに京都市内を望むことが出来るが、義政も東山殿を造営当時、工事の進捗状況を検分しながら、そこから戦火で家を焼かれて逃げ惑い、その日の糧を求めて彷徨っている多くの民衆の姿を見ていて何を思っていたのであろうか。そんな義政が詠んだ句が残されている。
「くやしくぞ 過ぎし浮世を 今日ぞ思ふ 心くまなき 月をながめて」
「わが庵(いお)は 月待山のふもとにて かたむく月の影を しぞ思ふ」
まさに明鏡止水と言ったような静かに澄んだ義政の気持が伝わって来る。
心身を脱落したような悟りの境地にも似た義政の枯れた美的感覚も見て取れる。
義政の遺言によって山荘であった東山殿を寺に改め、夢(む)窓(そう)疎(そ)石(せき)を開山とし、義政の法号である「慈(じ)照院(しょういん)殿(でん)喜山道慶大」から東山慈照寺(じしょうじ)と称した。
その後の戦乱で観音殿(銀閣)と東求堂(とうぐどう)だけを残して荒廃していたが、元和年間から寛永年間にかけて宮城丹波守豊盛等の尽力により復興し、現在に至っている。境内に入って先ず目に入る枯山水の銀沙灘(ぎんしゃだん)も砂で盛った奇抜な向(こう)月(げつ)台(だい)も其頃作られたものである。広く知られている「銀閣寺」という名称そのものも江戸時代に生まれたものである。
尾道の西国寺は天平年中(729~749)聖武天皇の時代に行基による開基とされている。
天仁元年(1108)白河法皇の勅願寺となり、その威光もあって官寺として百を超える末寺を持つ大寺となった。京都の上賀茂・下鴨神社が王城鎮護として皇室の尊崇を受けているが、この頃には既に西国寺には京都から「加茂神社」が勧請されている。
これは院政政権が官寺をアピールする為に意図的に作らせたのではないかと言われている。仁安元年(1166)には後白河法皇から西国寺に七帝の冥福を祈る為の不断経修行の命が下っている。正和元年(1312)には花園天皇の綸旨によって尾道浦を西国寺の寺領として賜った。
江戸時代の郷土史「尾道志稿」では「一息坂(坊地峠)に西国寺の門があり、寺の坊内ゆえ(このあたりを)坊地というとぞ」と記され、西国寺の寺領の大きさを伝えているが、現実的には距離が離れ過ぎていて無理がありこれはこじ付けであろう。
備後の守護山名氏は室町幕府の対明貿易に便乗し、尾道の港の権利を手にして貿易を行い巨万の富を手にしていた。
当時、尾道には「其阿弥」と称する刀匠の一派がいて、中国山地で産出される優良な砂鉄を使って玉鋼(たまはがね)を作り、尾道浦から十数万本の日本刀が輸出されていた。明国ではこの日本刀を神刀としてもてはやされたという。
当時、刀鍛冶集団が居たとされる現在の長江のバスプールの西側辺りを今も尾道では「鍛冶屋町」と呼んでいる。一方、明からは古銭(お金)を輸入して、日本の貨幣経済の一翼を担っていた。尾道市木ノ庄町では大量の明からの古銭も見つかっている。当時の遣明船は瀬戸内海航路用の大型商船を改造した千石積みの船で、尾道に船籍をおいた大船は四十五隻にも及んでいたという。
こうして得た財力で、永享年間には備後国の守護山名時熙(やまなときひろ)、持(もち)豊(とよ)(宗全)親子を始めとする山名一族はこの利権を保持しつつ、官寺として宗教的価値を持った西国寺に四十四年間にわたって莫大な寄付をしている。
この事はこの尾道浦を大田庄の倉敷地としてだけでなく瀬戸内海航路の中心的な中継基地として四国の讃岐を波頭とする細川氏にも対峙していたとも言える。現在でも広島県県下一の広大な敷地の中に、山名氏がスポンサーとなって有(ゆう)尊(そん)上人が復興した堂宇が天上世界として境内に建ち並んでいる。西国寺にはこの山名氏の寄付帳が残されており、この寄付帳は広島県の重要文化財となっている。
康永二年(1389)三月、山名時熙(やまなときひろ)(宗全の父)は義政の祖父である足利義満を厳島詣での帰路、前年に五重塔が完成し伽藍の整ったばかりの天寧寺に招いている。
永享元年(1429)、義政の父六代将軍義教が西国寺摩(ま)尼(に)山頂に建立したという三重塔の実質的なスポンサーも山名氏であった。お隣の三原市の備後一宮である御調八幡宮にも山名氏がスポンサーとなって嘉吉二年(1443)足利義政の名で奉納されたという木造の狛犬一対も残っている。
足利九代将軍となる足利義(よし)尚(ひさ)は父、足利義政と妻・冨子にとって待望の男の子であった。
自身の政治能力の力量に限界を感じていた義政は、文明五年(1474)に九歳の義尚に将軍職を譲った。父や母とは折り合いがうまくいかなかった義尚であったが、成長するにつけ学問を好み、十八歳の頃には私撰和歌集(新百人一首)を選定するほど和歌にも長じていた。若くして温厚にして文武両道に深く通じていたことで、下克上の高まりによって失墜した幕府の権威が回復しつつあった。
文明十二年には日野勝光の娘を嫁に迎え、守護大名達も徐々に義尚を「室町殿」と信頼するようになっていた。
しかし長享二年(1489)三月、近江南部の公家領や寺社の荘園を横領した近江国(滋賀県)の守護六角高頼(ろっかくたかより)を討伐するため、近江鈎(まがり)(滋賀県栗東市)に陣を張っていた時、義尚は突然意識を失って倒れ、脳溢血で亡くなってしまう。義尚二十五歳のことであった。
臨終に際して義尚は父に「ながらへば 人のおもひも見るべきを 露の居の命ぞ はかなかりける」(もう少し長く生きておれば世の中の色々な事が理解できたのに、もちろん親父とも分かりあえたであろうが、こんなにも早く死んでしまうのは本当に悔しい、残念だ。)との和歌を詠んでいる。
義尚が出陣に先立ち東山を訪れたのが今生の別れとなった。この和歌を受け取った義政は「埋(うもれ)木(ぎ)の 朽(く)ちはつべきは 残りゐ(い)て 若枝の花の散るぞ 悲しき」(私のような役立たずの年寄りが生き残って、将軍としてこれからという若い後継ぎが若い木が裂けるように苦しんで死んでしまった。天はなんとむごいことをするものか)と深い悲しみの歌を詠んでいる。
富子が後に詠んだ歌「さびしかれと 世をのがれこし 柴の庵に なを袖ぬらす 夕暮れの雨」(世を捨てて寂しい生活をしているのに夕暮れの雨が降って来てもっと寂しさが募って涙が溢れてくる。私には頼るべき夫も息子もいない)影響力の少なくなっていく富子の孤独さもひしと伝わって来る。
長享三年(1489)四月十日、義尚の葬儀が執り行われた。富子はこの葬儀については莫大な金額を提供している。
義尚には子供がいなかった。義政は義視の息子の足利義(よし)材(き)(義稙(よしたね))を養子として迎え入れて後継者とした。其頃から義政は中風の発作に苦しんでいた。義政は義尚の新盆を迎えるにあたり、相国寺七十九代住持・横川景三(おうせんけいさん)の進めで、如意ケ岳の山の斜面に白布をもって「大」の字を作らせ、東求堂から山面を望んで字の形を決め、斜面に七十五ヶ所の火床を掘らせた。
お盆の十六日にその火床に積み上げた松の割り木を一斉に点火して義尚の精霊を送った。現在の五山の送り火の始まりである。(但諸説あり)義政も次の年(1490)の一月(しょうがつ)、五十五歳で後を追うように亡くなっているので、彼が送り火を見るのはこの一度だけになるのであるが、赤々と燃えさかる送り火を眺めながらやりきれない諸行無常の念に苛(さいな)まれていたことであろう。

如意ケ岳(大文字山)
東山殿造営当時の遺構として現存する国宝・東求堂。その堂内にある四畳半の一部屋を「同仁斎」と言うが、この書斎で義政は茶を飲み、書を読み、香をたき、花を飾って過ごした。
義政の名付けたこの同仁斎の名は「聖人一視而同仁」(韓愈)より、誰彼の差別なく、全てのものを平等に愛することを意味しているという。波瀾の人生を歩んできた義政だからこそ、人生の肝要(かんよう)が「仁愛」であるとの心境に到ったのであろう。
近年の研究の結果、錦鏡池の浮石の上に十三夜の月の軌道が重なっていくことが解っている。中秋の名月の軌道ではなく十三夜の軌道というあたりに義政の美意識が見て取れる。
如何にもという満月よりも儚(はかな)い十三夜の月のほうが美の本質的な要素を持ち合わせている事に義政は気づいていたのであろう。そして移ろいゆくものを形に残して可視化しようとした義政の遊び心なのであろう。
四季折々の自然空間を巧みに取り入れたこの慈照寺の深い精神文化が日本の文化の母体となっていることは多くの人の認めるところである。しかしながら昨今、長い年月を経て築き上げてきたこの麗しい日本の文化が失われつつある。
グローバル化は競争社会を生み目先の利益に惑わされ、便利さやスピードが優先され、ゆとりが失われ、一人よがりな考え方が横行し、基本的な家族の絆さえも崩れかけている。
そんな時代だからこそ改めて日本文化の源流である処の日本の心ともいうべき義政の東山文化を今見直すことが求められているように思われる。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット